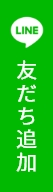Key Policy
強い高岡の構築 強い高岡の構築
これまでの実績
- 令和7年1月1日「震災復旧推進課」を新設し、4月には増員・機能強化により復旧作業を加速化
- 新たな避難場所「届出避難所制度」創設、16ヶ所認定済み(令和6年4月1日現在)
- 高岡版「マイタイムライン」を独自開発し、災害時の市民行動計画作成を支援
- 女性防災士の育成支援により、避難所運営に必要な女性の視点を確保する体制を整備
- 「高岡市防災士ネットワーク協議会」を発足させ、有事の際の連携体制を強化
- 社会的支援が必要な方の「個別避難計画」策定を県内で初めて先進的に推進 ⋯etc
今後すぐに始めていくこと
震災復旧復興と防災知識の普及・防災意識の変容
未来を見据えて取り組むこと
ハードもソフトも「強い高岡」の実現
【実現のための具体策】

強い高岡を構築するまち(15策)
-
令和6年能登半島地震からの一日も早い復旧、そして復興へ
令和6年能登半島地震からの
一日も早い復旧、そして復興へ令和6年1月1日午後4時10分。高岡市は観測史上初となる震度五強の地震に見舞われました。誰一人経験した事のない未曾有の大震災。地域も経済も行政も、そして私も初めての経験でした。それから1年が過ぎ、復旧は被災者の皆さんのご理解とご尽力、そして事業者のご協力のもと着実に進みました。ここからは復興を考えなければなりません。被災地が元気を取り戻す復興はもとより、震災を受けた市全体を「興す」事が重要です。被害の有無に関わらず、震災を乗り越え、新しい高岡を興すため、市民の理解を得て、挑戦、そして未来への循環を生み出し、他人に任せるのではなく、自ら勇気を持って進んでいけるよう、行政を動かし、その舞台を作り、支えることが私の役割です。「興」は字のごとく難しいものですが、前を向き突き進もうとする市民と共に、必ずや復興を成し遂げてみせます。
-
被災地の未来を住民と共に描く 地域復興計画の策定
被災地の未来を住民と共に描く
地域復興計画の策定発災後、大学生が地域に入り、被災地を調査し、被災者の声を聞き、現状を分析して、復興まちづくりを提案してくれました。行政だけではできない「地域と共に進めるまちづくり」計画であり、本当に心強く、ワクワクしながら計画を拝見しました。自分たちが住み続けるまちの姿を自分たちで考え、創り上げるという意思が伝わりました。このまちづくりの提案をベースに、どのようなまちを目指して行くのかを示す地域復興計画の策定に地域と共に取り掛かり、早期の事業化に向けて対応していきます。
-
インフラも心も「強い高岡」の構築
インフラも心も「強い高岡」の構築今回の震災で思った事は大きく分けて二つあります。まず、インフラを有事に備え、事前に強靭化しておくことで、復旧にかかる時間が短縮できるということ。二つに、いくらインフラが早期に復旧しても、市民の心が弱いままでは有事の度に同じことを繰り返す可能性が高いということです。そこで、高岡市震災復旧復興計画で「強い高岡の構築」を掲げ、ハード、ソフトの両面の強化をお示ししました。特にソフト、いわゆる心の部分は行政だけでの対応は難しく、市民お一人お一人がいつ来るか分からない災害について、正しく「恐れて」、正しく「備え」、正しく「行動する」ことが肝要です。例えば津波。津波は高岡市のどこを襲うのか、発災から何分で到達するのか、どの様な手段でどこへ逃げるのか、津波ハザードマップを今一度、読み解き、学んで、頭に入れる。これだけでも、津波未到達エリアの住民が来るはずの無い津波に備えて屋上へ逃げる事は無くなります。もし、来るはずの無い津波に備えて逃げた屋上で、熊本地震のように数時間後に一回目の地震よりも震度の大きい地震が来ていたら…どうなっていたのか…。いかに市民に正しく恐れてもらうことが重要か、身震いしました。この経験を活かし、市民お一人お一人がご自身の立場、状況、家族構成などから正しく備えることができる啓発活動、有事にどの様な行動を取るかを事前に確認できる環境整備に力を注ぎます。
-
命を守る!災害に備える市民意識のアップグレード
命を守る!災害に備える市民意識のアップグレード災害はいつ来るか分からないことを令和6年の元日に市民全員が身をもって経験しました。このことを風化させることなく、我がこととして捉えていくことが、防災の観点からも重要です。今回の地震で、「自分でやること、地域でやること、行政がやること」、また「自分でできること、地域でできること、行政ができること」が明確化しました。それぞれがより備えを強固にすることがまさに「強い高岡」です。立山連峰は貴方の命や大切な住居を守ってはくれません。都市伝説や思い込みを捨て、大切なものはみんなの創意努力で守るという市民意識の醸成を進めて参ります。
-
わがまち防災の推進による地域防災力の向上
わがまち防災の推進による地域防災力の向上日頃の備えの大切を認識した能登半島地震。その後、課題を分析し、避難所へのキーボックスの設置や自宅近くに設けることができる届出避難所制度の新設など、行政としての対応を進めています。一方で、指定避難所や届出避難所の運営については地域と共に進めなければなりません。日頃から、この避難所はどんな役割を担い、誰がどのように運営するのかを役割を担う当事者だけでなく、避難する地域住民と共有しておくことが必要です。訓練を一度行えば全て身につくものではなく、繰り返し、何度も確認することではじめて身に付きますし、ヒトの入れ替わりが想定されるため、個人で役割分担するのではなく、役職で分担すべきとも考えます。誰が運営責任者になっても、等しく運営できるのが最適です。そのためのシミュレーション訓練が行えるよう体制を整備し、より具体的な訓練を各地域で行い、地域防災力の向上を目指します。
-
指定避難所の機能強化とわがまち避難所(届出避難所)整備推進
指定避難所の機能強化とわがまち避難所(届出避難所)整備推進震災後、資器材の搬入や仮設トイレの設置等、災害時の支援体制について民間企業と協定を結ぶなど備えの強化に努めています。同時に進めなければいけないのは、届いた物資の仕分けやトイレの設置場所の選定などについて、避難所運営側と事前に話し合うことです。指定避難所の機能を強化するための事前協議を地域の協力のもと進めていきます。また、指定避難所への避難には、時間も労力もかかるため、「逃げない」という判断をされた方も多くおられました。自宅から最も近い自治公民館(耐震性有の場合)を届け出る事で避難所として開設できる取り組みを新たに設け、既に16ケ所(4/1現在)を認定しました。今後も命を守る取り組みとして、一か所でも多くの「逃げる判断のできる避難所」を増やしていきます。
-
作りたくなる「マイタイムテーブル」の作成と市民周知策強化
作りたくなる「マイタイムテーブル」の作成と市民周知策強化有事の際にどのような行動をとるかを事前に家族で話しあって作成する「マイタイムテーブル」。これは有事の際に、携帯電話が通じない場合にも、事前に決めておいた行動を取る事で、大切な家族と離れ離れにならないためにも有効です。一方で、実際に「作成して家族と共有した」とのお話はまだまだ少なく、その必要性を知っていただく必要を感じています。作りたくなる、作らなければいけないと思ってもらえる「高岡版マイタイムテーブル」を独自に開発し、市民への周知と作成率の向上を目指します。
-
社会的に支援が必要な方への個別避難計画の策定推進
社会的に支援が必要な方への個別避難計画の策定推進避難を考えた際、自身の力だけでは逃げることが難しい方がおれます。社会的に支援が必要な人をいかに守るか、守ることができるか。守るためには事前に確認すべき事が沢山あります。誰がどのような支援を行い、どこへ避難するのかを明確に示す個別避難計画を事前に作成しておく必要があります。高岡市では地域ミーティングを県内で初めて実施するなど、計画の策定に向け先進的に取り組みを進めています。今後は計画の必要性について当事者を始め、地域に協力を呼びかけ、先行する地域を創り、成功事例を地域間で横展開し、計画策定を推進していきます。
-
女性防災士が活躍できる環境整備と人員増加策の展開
女性防災士が活躍できる環境整備と人員増加策の展開人口の半分以上が女性の高岡市にあって、避難所に来られる市民の男女比を考えても、避難所運営には女性の観点が不可欠です。市民の中でも防災知識を持った女性防災士の方にはまさにその役割を担っていただきたいと考えています。地域女性ネット高岡では女性防災士の育成を目指し、積極的に取り組んでいただいており、大変心強く思っています。より女性防災士が増えるための施策を検討しつつ、肝心なのは有事の際に、女性防災士が避難所運営に欠かせない存在であることを運営する地域や役員がしっかりと理解し、一緒に運営に携わってもらえる環境の整備です。女性防災士の必要性を訴え、地域の理解を拡げ、活躍していただける環境整備を進めます。
-
防災士を各地域、各避難所へ 防災士ネットワーク協議会との連携強化
防災士を各地域、各避難所へ 防災士ネットワーク協議会との連携強化防災士が各地域で等しくご活躍いただく事は災害への備えや有事の際の対応などにも大きな効果があります。一方で、地域の人口バランスや年齢構成などもあって、全地域で今すぐ防災士を確保できるわけではありません。能登半島地震発災時、防災士と行政が連絡を取り、何かを依頼できる関係が構築できていない事が判明しました。その後、有志の防災士の方々に対し「連絡が取りあえる関係の構築」を呼びかけた結果、「高岡市防災士ネットワーク協議会」が発足しました。今後は有事の際に防災士不在の地域や避難所に派遣いただける関係を構築するなど、連携強化を図ります。
-
防災士が真に防災士として活動できる役割分担の徹底
防災士が真に防災士として活動できる役割分担の徹底防災士は防災知識や避難所運営等の専門的知識についての講習と試験を突破した方々です。強い高岡を構築する上で、大切な人財であり、防災士の活躍は必要不可欠です。私も一人の防災士ではありますが、同時に悩みもあります。「試験は通ったが、自分の知識は正しく合っているか、それは正しい判断なのか」まずは、自分の知識に疑いを持ち、確認して実行しなければ、結果、思い込みなどの間違った判断に繋がるものです。日頃から防災知識の確認ができる研修の体制をしっかりと取る事は「真に活躍」する上で重要です。また、防災士は何でも屋ではありません。防災士が訓練や避難所で果たす役割についても確認しておくことは重要です。避難所運営にあたる防災士の役割についても事前に協議できるように努めます。
-
有事に支援が確実に届く自治体間の支援体制の強化(強い高岡)
有事に支援が確実に届く自治体間の支援体制の強化(強い高岡)今回の地震では沢山の支援をいただきました。中でも、人的支援や物資・資器材の支援については災害協定都市の他、面識のある同志の首長に直接連絡をして、即時対応いただく局面もありました。本当に多くの自治体や企業からご支援を頂き、被災地、被災者を代表して御礼に伺いました。その事に対して、「御礼に直接行く必要が無い、オンラインで言えばいい」「御礼にかける時間も費用も無駄」とのご指摘を市民の代表である議員の一部やマスコミからいただきました。根本的に考え方が違うので、否定こそしませんでしたが、被災者、被災地の皆さんも同じ思いでしょうか。私は被災地の皆さんが受けた支援に対し、地方公共団体の長が御礼をする事は当然の礼儀だと思っています。これからも直接、頭を下げて、感謝を伝える事のできる市長でありたいと思います。そのことが今後の自治体間の信頼関係や災害協定都市の締結、そして次の支援に繋がると確信をしているからです。今後は災害の同時発生の可能性が比較的に低く、「陸路の地の利」がある東海エリアを中心に、災害時に支援を頂ける自治体を増やすため、全国青年市長会東海エリアの首長との連携を深めていきます。
-
震災復旧推進課の機能強化による復旧加速化
震災復旧推進課の機能強化による復旧加速化震災から一年が経つ令和7年1月1日。高岡市役所に新しい組織「震災復旧推進課」を設置しました。一年が経ち、復旧が進む中、今後もよりスピード感を持って、被災地に寄り添って復旧を進めたいという強い想いを示し、実行するためです。4月には人的な増員や機能の強化を図り、一日も無駄にしない、二度手間を避けるなど効率も高い復旧工事をより具体的に検討し、一日も早く復旧が完了するよう震災復旧推進課を先頭に全庁を挙げて努めて参ります。
-
大雪時の除雪体制強化など有事に強い体制構築
大雪時の除雪体制強化など有事に強い体制構築震災や津波、大雨だけが災害ではありません。大雪も本市にとっては災害の一つです。能登半島地震の際、大雪に見舞われなかった事は不幸中の幸いと言えます。これまで早期の出動判断や除雪機へのGPS搭載など大雪への体制を整えてきましたが万全とは言い切れません。どんな時も雪に強い高岡であるために、除雪体制の見直しや高齢化が進む除雪事業者の若返りを含めた人材確保など、様々な災害が複合化する事も視野に入れ、より有事に強い体制を構築していきます。
-
命の道路 東海北陸自動車道の早期四車線化と能越自動車道の全線開通
命の道路 東海北陸自動車道の早期四車線化と能越自動車道の全線開通震災時、人的支援、支援物資は陸送でやってきました。まさに道路が命を繋ぎました。中でも東海北陸自動車道や能越自動車道は能登半島地震において命の道路としての役割を十二分に果たしていました。一方で両道路には課題もあります。東海北陸自動車道については早期の4車線化、能越自動車道についてはまだ繋がっていない区間(ミッシングリンク)の早期整備や暫定二車線の道路については付加車線整備からの四車線化を目指して進めていく必要があります。今後も国や関係機関への要望活動を継続的に行い、被災自治体を代表して早期の完成を強く呼びかけていきます。
Key Policies