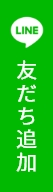Key Policy
こどもまんなかの実現 こどもまんなかの実現
これまでの実績
- 保育士等就業支援制度を県内初導入し、50人超の新規採用を実現。働きやすい保育現場づくりを推進。
- 出生届オンライン申請を全国に先駆けて導入。産後ケアと合わせ子育て支援を強化。
- 不妊治療で年齢・居住制限撤廃や治療費助成で経済的負担を軽減。
- こども食堂・ふれあい食堂を拡充し、地域ぐるみで子どもを支える環境を整備。
- 高岡市で地域で支える子育て世帯の食支援「ベビーファーストこどもごちめし高岡」プロジェクトがスタート!
- タブレット端末更新費用を基金化し、計画的なICT環境整備を推進。
- 「高岡市こども計画」を策定し、こどもの権利を重視した施策を推進⋯etc
今後すぐに始めていくこと
大人が責任を持って『こども「を」まんなか』に
未来を見据えて取り組むこと
子どもの夢を真剣に応援「夢叶うまち高岡」へ
【実現のための具体策】

大人が責任を持って取り組むまち(14策)
-
子どもたちが実感できる『こども「を」まんなか』に据えた施策の推進
子どもたちが実感できる
『こども「を」まんなか』に
据えた施策の推進「こどもまんなか」や「ベビーファースト」など、当たり前の事を口にしないと行動できない時代になったことを本当に恥ずかしく思っているのは私だけではないと思います。少子化が進む中、このままの状態で次代に託すのか、それとも今を生きる私達大人が責任を持って立て直し、堂々とバトンを託すのか。こどもはこどもだけでは真ん中にはなりません。大人がこども「を」まんなかに据えて何事も考えていく、そしてそのことが実体験を持って、子どもたちに伝わらなければなりません。市役所の全事業に子ども視点を加えたように、このまちで起きる全てに「こども」を考えて実践できる社会の構築を目指し、『こども「を」まんなか』に据えた施策を展開していきます。
-
地域の宝物である子どもを育む保育士等への支援策の充実
地域の宝物である子どもを育む保育士等への支援策の充実子どもは地域の宝。この4年間口すっぱく伝えてきた事の一つです。そしてその子どもを預り導いてくれる学校の先生や保育士などの皆さんには子どもと全力で向き合える環境を整えたいと考え、小中学校へのI CT導入や保育園支援システムの導入等、働き方改革を進めてきました。一方で、保護者の立場からは保育士不足を理由に「行きたい園の定員が増えずに第一希望の園に入園できなかった」とのお話をいただくこともありました。高岡市で子どもと向き合う人を増やしていきたいとの思いから保育士等就業助成事業を県内で初めて導入し、これまでに50人を超える新規採用の保育士等が誕生しています。今後も地域の宝を育むための施策を積極的に打ち出し、こどもの成育を支えて参ります。
-
不妊治療への市独自支援策の継続とさらに効果的な支援策の検討
不妊治療への市独自支援策の継続とさらに効果的な支援策の検討高岡市は令和3年から2年連続で出生数が1000人を上回る増加傾向でしたが、令和5年度の出生数は800人台まで減少しました。理由については、コロナ5類移行で通常の生活が始まったことや物価高騰などの不安定な社会情勢が背景にあると分析しています。高岡市では子どもを望み、不妊治療を行っている方の負担をより軽くすべく、一般的な治療が健康保険の適応になった後も、本市独自策として、助成対象の拡充や年齢制限の撤廃、住居要件の緩和など支援を続けてきました。これらにより治療を継続される方が一定数確保できた一方で、出生数は伸び悩んでいます。子どもを取り巻く支援策の見直しや追加などが必要ですが、不妊治療に関しては、今後も市独自の一般的な不妊治療への助成制度を継続するとともに、市内では受ける事のできない難易度の高い不妊治療を望み、県外の医療機関で治療を受けておられる方、望まれる方への助成拡大を視野に入れ、出生数が増加傾向に戻れるよう努めて参ります。
-
女性が心と体が健やかに「産んで、育てて、働ける」社会の実現
女性が心と体が健やかに
「産んで、育てて、働ける」
社会の実現子どもを産むことは女性が命を掛けて臨む人生の転機です。コロナ禍の中、たった一人で息子を生んでくれた妻からその覚悟と偉大さを感じました。産後は慣れない子育てと同時に親として出生届などの行政手続き等が始まります。高岡市が産後ケアに力を入れるのも、全国に先駆けて出生届のオンライン申請をスタートさせたのも、体調も完全では無い中で、少しでも負担を軽くし、子どもと触れ合う時間を取って欲しいとの思いがあるからです。心と体が健やかな状態で、子育てや社会復帰等、ご自身が望まれる時間を過ごして欲しいと願っています。「母だから…」「女性だから…」を理由に何かを諦めなくていい、女性が望む社会の実現を目指し、今後も産後ケアをはじめ、様々な支援策を充実します。
-
保育料、副食費無償化に向けた取り組み推進
保育料、副食費無償化に向けた取り組み推進子育て世帯の負担を軽くすることを目的に保育料や副食費の無償化を進めてきました。完全無償化には多額の財源が必要であり、一度無償化に踏み込めば恒久的な事業として、将来に渡って財源確保が必要です。そのためには子育て世代だけでなく全ての市民の理解が必要です。これまで第三子以上や第二子への支援が多く、第一子への支援については子どもの数の少ない小規模な自治体では実施できても、一定程度の人口規模のある自治体ではなかなか踏み込めない状況でした。一方で、日本一財源に恵まれた東京都は様々な無償化を進めていますが、出生率は「1」を割り込みました。これは無償化が少子化対策の一丁目一番地ではない可能性を示唆しています。高岡市では昨年度から所得制限はあるものの、第一子への支援をスタートさせました。今後は第二子出生数の変化等の効果を検証し、今後の施策の方向性を決めて、より効果的な少子化対策の取り組みを推進していきます。
-
公的・民間学童保育の体制強化とこどもの居場所確保事業の拡大
公的・民間学童保育の体制強化とこどもの居場所確保事業の拡大放課後の子供たちの居場所確保は共働き世帯が増える中で、重要な行政サービスです。居場所の一つに学童保育があります。公的学童保育は利用料こそ安価な一方で、定員の壁があり、希望する全ての方が入所できていません。市議会議員時代に公的学童に入所できない保護者の相談を受け、高岡市で初めて民間学童保育を誘致しました。民間学童は学習サポートやスポーツ等の習い事の要素を持った付加価値がある反面、利用料は公的と比較すると高くなります。また、公的学童では預かり時間が短く、保護者にとっては短時間勤務による収入減などの課題もあります。保護者には収入を得て、民間学童を選択するか、短時間勤務で公的学童を選択するか、難しい判断が求められます。今後も公的・民間学童保育の体制を強化すべく、支援員をはじめとした人材確保への支援や民間学童保育の利用者への負担軽減策などを実施し、こどもの居場所作りを加速していきます。
-
子ども食堂、ふれあい食堂等による大人と子どものきずな構築事業支援
子ども食堂、ふれあい食堂等による大人と子どものきずな構築事業支援市内では、子ども食堂が増えてきており、子どもの居場所が増えたことを大変嬉しく思い、関係各位には心から感謝と敬意を表します。さらには、子ども食堂の進化系として、子どもと高齢者の憩いの場として、地域交流センターにてふれあい食堂を開催されている地域もあり、地域の絆作りに貢献されています。今後はより多世代が交流できる場として、また社会的な課題を抱えた子どもを見つける、救う場として、社会協議会との連携のもと、より広がりが生まれるように各種支援策を進めて参ります。
-
本当に支援が必要な子どもへ直接届く善意の輪「ごちめし」普及
本当に支援が必要な子どもへ直接届く善意の輪「ごちめし」普及子ども食堂を巡っては、新たな課題も顕在化しています。本来は貧困家庭への支援として始まった子ども食堂ですが、誰もが参加しやすい環境作りを進める中、憩いの場としての側面が強くなり、本当に支援が必要な子どもや世帯に対し支援が届いているかという課題です。自分が貧困世帯だと知られたい人はいません。いかに周りに分からない状況で支援を受けられるかを考えなければいけません。全国で新しい子ども食堂の手法として「ごちめし」というサービスがあります。これは企業等からの寄附を財源に、貧困世帯へ、食事ができるデジタルチケットを配布し、参画している飲食店において食事を摂れるというものです。この「ごちめし」を高岡市でも導入したいという民間企業と行政が連携し、新しい子ども食堂の形として普及させ、真に助けを求めている子どもへ直接、支援を届けていきます。
-
こどもとお年寄りがコラボ!eスポーツ等を活用した子どもの居場所づくり
こどもとお年寄りがコラボ!
eスポーツ等を活用した子どもの居場所づくりふれあい食堂のように、こどもと高齢者を対象にした事業や三世代交流などの多世代が交流する事業を推進してきました。今後は学童保育の充実と並行して、地域の高齢者と子どもの交流を進めていく事で、小学校高学年の子どもを対象とした居場所作りも進めていきます。そこで注目したのが、eスポーツです。高岡市老人クラブ連合会ではeスポーツの普及にご尽力いただいており、高岡市の支援制度を利用された各地域の老人クラブが地域交流センターでeスポーツを楽しんでおられます。ここに、さらに視点を加え、eスポーツの講師として地元の子どもたちを招き、一緒にクラブを立ち上げるなど、交流が生まれる事業を創出します。その結果、子どもの居場所が増え、高齢者の方の生きがい作りにもなり、地域活動の活性化にも繋がるといった好循環を生み出すことのできる事業を進めていきます。
-
多機能自治へと挑戦する先進自治会へのインセンティブ事業
多機能自治へと挑戦する先進自治会へのインセンティブ事業「地域の事は地域の方が一番分かっている」との思いから、現在、自治会が抱えている「担い手不足」の課題解決を目指し、多機能自治の導入を推進しています。現在、自ら挑戦を決意された4地区が先行的に取り組みを進めています。実証から実装へと移る中、行政としては挑戦意欲ある自治会に対して、より強い地域を構築していただきたく、インセンティブ事業を検討し、強く後押ししていきたいと考えています。人口減少は待ったなしの課題であり、地域の存続は人口減少とリンクしています。地域の存続をかけ、危機感を持って取り組む自治会をしっかりと支えて参ります。多機能自治は、地域の未来の形を描き、その必要性や運営する上でのメリット、デメリットもしっかりと受け止めるところから始めていかなければなりません。先進地域も勉強会を重ね、全国の先進例や地域課題を抽出し、住民理解を高めた上でスタートしました。今後は先進地域が変わっていく姿を他自治会にも共有することで、「自分たちにもできる」と感じていただき、挑戦してもらえるように環境整備も進めていきます。
-
若い人が参画できる自治会へ 地域の担い手育成・確保事業
若い人が参画できる自治会へ 地域の担い手育成・確保事業昨年実施した「若者地域活動支援補助金」は多くの地域でご活用いただき、地域の若者と自治会や地域を繋ぐ機会の創出に寄与しました。この流れを加速すべく、新年度は事業を行う上で発生するイニシャルコストとランニングコストに分けた形の支援策を打ち出しました。生まれた地域の事業を支援しつつ、新たな挑戦を生み出す仕組みです。今後はイベント開催に留まらず、生まれた繋がりを活かし、自治会運営にも若い世代が参画できるようにしてく必要があります。若い世代の意見に耳を傾け、何を変える事で働き世代の若い人が運営に参画できるのか検討する必要があります、市連合自治会と連携を図りつつ、役員担い手不足や若い世代の自治会離れを解消し、持続可能な自治会運営を検討していきます。
-
多文化共生を目指した相互理解の場の創出
多文化共生を目指した
相互理解の場の創出高岡市には現在4000名を超える外国籍市民がおられます。人口の3%が外国籍市民であり、暮らしの場を共有していく上で、相互理解を進める事は大切です。言語や文化は違えども、同じ人間。相手を「おもいやる気持ち」を持ち、相手を「受け入れる器」を持てば、多文化共生は必ず実現できます。ゴミを1つ捨てるだけでも国によってルールは違います。自治会という組織も外国には存在しないのかもしれません。日本人が「多文化を受け入れ」、外国籍市民が「日本のルールや慣例を理解する」ところから始め、多文化共生を図っていきます。
-
外国籍市民の力を借りて国際感覚を持った市民意識の醸成
外国籍市民の力を借りて国際感覚を持った市民意識の醸成高岡市で暮らしていく上では国際的な感覚はそこまで必要ないかもしれません。では、こどもたちはどうでしょうか?国際化が進み、デジタル技術が日進月歩する中、職業の選択にあたっても国内に留まらず、世界に羽ばたく人が増えています。子どもたちがどんな選択をしても、国際感覚が身についていれば、より夢は叶いやすくなります。高岡市には国際感覚を養う上で、力を貸して下さる外国籍市民が沢山おられます。是非、力を借りましょう。知人のパキスタンの方は震災後、誰よりも被災地のために活動されていました。その心は国境を超えます。高岡市内には国境はありません。外国籍市民との交流を通じて、市民の国際感覚を磨き、共に生きるとの意識の醸成を図ることで、「国境なき高岡市」を目指します。
-
地域交流センターを地域交流拠点と稼ぐ施設に 地域交流センター活用策の推進
地域交流センターを地域交流拠点と稼ぐ施設に 地域交流センター活用策の推進地域の活性化は高岡市の地方創生の一丁目一番地です。地域では担い手不足などの課題解決に向け、様々な取り組みが進められていますが、何かを行うときには資金が必要になります。地域が必要な財源を確保する手段として、地域交流センターの貸館事業を始めとした稼ぐ施設化を進める必要があります。施設の貸館事業は外からの風を吹き込み、地域の交流促進など活性化にもつながります。地域の稼ぐアイディアを実現できる施設へ、もっと地域に愛される施設へ、地域交流センターの活用策を推進します。
子育てや教育の環境が充実したまち(20策)
-
全国唯一のものづくりデザイン科授業の進化
全国唯一のものづくりデザイン科授業の進化ものづくりデザイン科は小学校5年生から中学校1年生までを対象に、高岡の伝統工芸に触れ、ものづくりへの関心を持ち、資質・能力を育成することを目標に平成18年にスタートした全国唯一のカリキュラムです。開始から20年の間に学習指導要領も改訂され、高岡市では論理的コミュニケーションやタブレット端末の導入など、子どもたちの教育環境も大きく変わっています。着実に伝統産業への理解が浸透していく中、ものづくりデザイン科授業がこの先どうあるべきか、子どもたちに何を学び、育んでもらうのか、伝統産業界の皆さんや教育委員会とともに、今の時代に、より「刺さる」授業へ進化させていきます。
-
学校再編の着実な推進と跡地利用策の同時進行
学校再編の着実な推進と跡地利用策の同時進行少子化や人口減少に伴い、児童数は減少傾向にあります。現在、子どもたちの学びの環境を維持・発展を目指し、学校再編を進めています。再編については、地域やPTAの皆さんのご理解とご協力をいただき、着実に進んでいます。ご協力に感謝申し上げます。一方で、これまでは再編を最優先とし、学校跡地の利活用については再編後に検討することとされていました。跡地利用についての協議の場では「学校建物が残されないのなら、学校再編に賛成しなければ良かった」「思い出のために校舎を残して欲しい」など、耐久年数やその解体にかかる費用などは度外視され、子どもたちのための学校再編にすら否定的な意見が出るなど正常な議論とは言い難い状況も一部に起きていると感じました。もちろん学校が地域にとって大切な場であることは重々理解していますが、単にそのまま残すことは今後の解体費や維持費などの負担を将来世代に強いる事になり、その責任は誰がとるのでしょうか。私たちがしっかりと整えた上で、次の時代に託さなければならない。その想いから、再編統合の議論と同時に跡地の利活用策についても議論すべきと判断し、今後の再編統合においては同時進行で進めていきます。
-
児童生徒タブレット端末の計画的な更新と有効活用
児童生徒タブレット端末の計画的な更新と有効活用児童生徒の一人一台タブレットが支給されて5年が経過します。多額の予算が必要になる更新の時期が迫る中、いかに単年の負担を小さく、また遅れることが無いように進める方法を模索してきました。単年で予算化するのではなく、更新にかかる費用を複数年に渡って基金として積み上げることで、財政負担を平準化して対応することにしました。その結果、学校教育振興基金4.3億円を活用して、今年度、単年の負担も最小限で抑え、遅れることなく更新することができます。また、不要となったタブレット端末については庁舎内における市民サービスのデジタル化やデジタルに対して苦手意識のある高齢者の皆さんのために有効に活用できないか、検討を進めています。
-
プログラミングをもっと身近に誰でも参加できるワークショップの開催
プログラミングをもっと身近に誰でも参加できるワークショップの開催学習指導要領の改訂により、プログラミングが必修化され、子どもたちのICT教育は加速的に進んでいますが、得意不得意も出てきています。得意な子は世界大会に進出するなど成果を出している一方で、苦手意識を持つ子どもの親からは「どうすれば楽しめるようになるのか」などの相談をもらっています。授業として取り組むだけでなく、自分の関心事として楽しめることも重要であり、誰でも気軽にプログラミングに触れ合える、参加しやすいワークショップを立ち上げるなど、こどもたちがプログラミングをもっと身近に楽しめる機会を創出していきます。
-
学校トイレの洋式化の推進と実施計画の周知
学校トイレの洋式化の推進と実施計画の周知学校や保護者からの要望においてトイレの洋式化推進の声をいただきます。今の時代に応じた必要な施策であり、教育委員会でも計画的に実施していますが「うちの学校はまだなのか」「全学年のトイレでの実施を」との声があり、洋式化の計画が浸透していないこと、要望と実施のスピードが合っていないことを感じています。学校には老朽化や教育環境の変化から様々な更新が求められていますが、全てを実現するためには多大な費用も掛かるため、計画的に進めなければなりません。今後は各学校における工事の見通しを示すなど、学校関係者の理解と協力を得て、着実に推進できるよう関係を構築します。
-
温暖化対策や防災の観点から体育館への空調設置に向けた検討
温暖化対策や防災の観点から体育館への空調設置に向けた検討これまで体育館の空調設置については多額の費用が要する事から、まずは普通教室や特別教室を優先してエアコンの設置を進めるとともに、学校再編に伴う新校舎や体育館については将来の空調設置を見込み、断熱構造を採用するなど対策を講じてきました。教室へのエアコン設置について一定の目途が立ったことから、いよいよ体育館に関して、費用面やエネルギー効率などの調査を始めます。また、体育館については災害時の避難所にもなることから、温暖化や酷暑対策の他、防災の観点からも空調設置の検討を進めて参ります。
-
富山県のこども条例と連携・連動したこども計画の推進
富山県のこども条例と連携・連動したこども計画の推進高岡市では今年「高岡市こども計画」を策定しました。計画では子どもたちの権利を守りつつ、子どもたちへの各種支援施策をより推進していくことにしています。また、県が制定に向け進めている「富山県こどもの権利に関する条例(仮称)」の状況を注視しつつ、制定後は県の施策と連携・連動を則り、高岡市においてもこどもの権利が守られ、こどもの願いが叶う施策を推進していきます。
-
病児保育や病後児保育などへの対応強化型施設となる拠点保育所を整備
病児保育や病後児保育などへの対応強化型施設となる拠点保育所を整備保育ニーズの高まりや複雑化によって、保育サービスの棲み分けが求められています。まずは市立園と私立園の役割分担を検討していくことが重要です。例えば、病児・病後児や障がい児保育など、より複雑な保育ニーズに関しては市立園が中心となって保育サービスを提供し、私立園は希望する子どもの受け入れに注力するなど、より一層、連携して保育サービスを充実させていきたいと思います。また、市立園に関しては、保育園の機能強化を目的とした再編についても検討し、より複雑なニーズにもワンストップで対応できる拠点保育施設の整備を検討し、対応を強化していきます。
-
外国籍児童の日本語教育推進に向けた体制強化
外国籍児童の日本語教育推進に向けた体制強化高岡市には現在200人を超える外国籍児童・生徒(母語11言語)が各学校に通学しています。各学校には外国籍児童相談員が訪問し、お知らせの翻訳や外国籍保護者と学校との間で相談に応じたり、日本語を教えたりしています。各学校をきめ細やかに対応していただいている一方で、プリントの翻訳など各学校で同じ作業に対応するなど効率の悪さも指摘されています。今後はより外国人相談員の方々が子どもと向き合う時間を持っていただけるように改善していくとともに、日本語教室に関しては教育総合支援センター(仮称)内に拠点となる教室を設け、より日本語習得に向けた対応を強化し、各学校で児童のコミュニケーションが円滑に図られるよう努めます。
-
いじめ対策 県との連携強化でセーフティーネット形成
いじめ対策 県との連携強化でセーフティーネット形成いじめや暴力はどんな理由があっても絶対に許される事でありません。各学校では先生方は細心の注意を払っているものの、いじめが無くならないのが現実です。県による調査では令和5年度に認知したいじめの件数は3100件と前年の1.57倍に増えています。いじめを発見し減少させるためには、学校にのみ対応を任せるのではなく、全県的なセーフティーネットを設けられないのかと考え、ワンチームとやま推進本部でも知事に訴えました。県では富山駅前にこどもの相談窓口を設置するとのことですが、場所は富山市、空いているのは平日日中となっており、子どもが本当に使用しやすい環境なのかを検証しなければなりません。また、改善策として相談LINEや24時間365日つながる専門ダイヤルの整備など、子どもがいつどこででもSOSできるセーフティーネットの構築を県や他市町村と連携して進めます。
-
いじめや不登校などの教育課題解決を目指す教育総合支援センター(仮称)を開所
いじめや不登校などの教育課題解決を目指す教育総合支援センター(仮称)を開所現在、旧平米小学校の校舎の一部を活用して、教育総合支援センター(仮称)の設置を進めています。このセンターはこれまで高岡には無かった施設で、様々な教育的課題を解決するための拠点です。いじめ、不登校、発達障害、日本語教育など教育を取り巻く課題は尽きません。今日よりも明日、子どもたちが希望を持って暮らせるように、教育総合支援センター(仮称)を早期に稼働させ、教育課題への対応を強化していきます。
-
家庭環境に関わらず子どもが習い事に通える支援策の実施
家庭環境に関わらず子どもが
習い事に通える支援策の実施子どもが抱いた夢の実現に必要となる習い事は、親としては通わせたいと願うものです。しかし、何らかの事情によって、通う事が叶わず、夢を諦めてしまっている現状もあります。義務教育で全ての学びが提供できるわけでなく、希望する教育を受けることができる補填事業を起こし、夢を叶える支援として家庭環境に関わらず通える環境整備に向け、県と連携し支援を進めていきます。
-
民間スポーツジムや水泳協会と連携し、子どもの安全確保と水泳力強化
民間スポーツジムや水泳協会と連携し、子どもの安全確保と水泳力強化学校プールでの事故を無くすため、これまで学校と保護者が力を合わせて監視体制を構築していました。ご協力に感謝致します。水の事故は夏のレジャー時期などでも発生する可能性があり、子どもの安全確保と水泳力強化は命を守る上で重要です。一方で、学び場となる学校プールは老朽化も著しく、環境改善には時間とお金がかかります。また、学校教諭による水泳指導には限界もあり、より専門性も求められています。これらを解決する手段として、現在、複数の学校を対象に、スポーツジムや水泳協会と連携した水泳授業の実証実験を行っています。これにより屋内プールの利用ができ、年間を通して授業を行うことができるほか、プロが講師となるため、子どもたちの水泳力強化が見込めます。また、多額のプール修繕費用が抑えられるなどの効果も望めます。今後はスポーツジムから遠いエリアにおける移動手段や更なる水泳協会との連携による授業の在り方についての検討など、時代に求められる水泳の授業を模索して参ります。
-
地域部活動の競技種目を増加 文化系部活動への導入検討
地域部活動の競技種目を増加 文化系部活動への導入検討少子化に伴い、中学校部活動は転換期を迎えています。各学校単位の実施では活動できない競技が増え、複数校での実施やクラブチーム化を検討する必要もあります。地域部活動へ先進的に取り組みを進めてきた本市では、今後も子どもたちがどこに住んでいても挑戦したい部活動が行える体制づくりを各スポーツ団体と連携し取り組んで参ります。一方で、体育系の部活動での地域部活動化が進む中、文化系にも広げていかなければなりません。文化のまちである高岡市の所以も活かし、茶道や書道の講師を務めていただける人財の宝庫ですし、ものづくりのまちの特性を守るためにも化学部や美術部などの存続も重要です。今後は文化系部活動にも地域部活動の導入を強化し、部活動を進化させていきます。
-
アメリカや台湾等姉妹都市や友好都市とのスポーツ交流
アメリカや台湾等姉妹都市や
友好都市とのスポーツ交流アメリカや台湾を訪問させていただき、飛行機の座席の話題が取沙汰されました。お騒がせしたことを大変申し訳なく思っています。一方で、内容についての議論や報道が少なく、大変残念でした。市長として本市に必要な国際交流を今後も引き継ぐべきとの考えで訪問し、各国との共通点や今後の可能性を交渉してきました。言語や文化を超えてできる交流の一つにスポーツがあります。訪問したいずれの国にも夢を追い、白球を追いかける球児の姿があり、野球交流への可能性を感じ、交渉に臨みました。その結果、野球における国際交流について賛同を得ることができ、今後、高岡市において、日米台の高校生による親善野球大会の実施などを進め、国際感覚の育成と競技力の向上を目指します。
-
英語を「学ぶ・覚える」から「使う・慣れる」への進化教育の実践
英語を「学ぶ・覚える」から「使う・慣れる」への進化教育の実践「英語をもっと学んでおけばよかった」こう思うのは私だけではないはずです。アメリカを訪問した際、改めて強く感じましたし、「どうすれば一番吸収できる時期に生の英語を体感し、身につける事ができるのか」「読み書きのみの詰込みではなく、日常的に使って、英語を話すことに慣れることはできないか」を考えました。本来、大学間の連携の話を進める予定で渡米しましたが、協議の場で高校生以下でも連携ができないかと提案をし、日本初の高校生向けの英語習得プログラムの開発や小学校間の英語による国際交流について合意し、市内県立高校や小学校で交流が始まっています。これらを更に広げ、高岡市の英語教育を進化させていきます。
-
必要とされる高等教育の在り方を検討し、大学誘致や設置を検討(教育)
必要とされる高等教育の在り方を検討し、大学誘致や設置を検討(教育)高岡市唯一の私立大学であった高岡法科大学が学生募集を停止し、3年後には閉校を迎えます。無くなることを問題視し、大学の設置や誘致を訴える方もおられますが、なぜ閉校に到ったのかを冷静に受け止めなければなりません。今回の件が表面化する以前から市内経済人と共に、理系大学の誘致を目指して、私立大学の意見を聞いてきました。全国各地の地方大学では少子化の煽りを受け、定員割れ等大変厳しい状況の大学もあれば、カリキュラム等の積極的な見直しにより人気を集める大学もあります。人気の大学はカリキュラムから卒業後の就職まで一貫したプログラムを構築しています。例えば、市立三条大学のような学長の情熱によって道を切り開き始めている大学は地方大学のあり方を検討する上で、大変参考になります。同じものづくりのまちである三条市等の協力を得て、高岡市の産業や人口構造などを踏まえた上で次代に必要とされる高等教育のあり方を検証し、大学の設置や誘致を含め検討を進めます。
-
自宅や学校以外でも勉強・学習できる場所の拡充
自宅や学校以外でも勉強・学習できる場所の拡充高校生と話をすると「図書館で勉強したくても場所が少ない」といった声を多数聞きました。
そこでスタートアップ施設「TASU」を整備する際、勉強や学習に使う事ができるフリースペースを設けました。多くの学生に利用を頂いており、「市長に声が届いた」と学生からSNSを通じて喜びの連絡をいただきました。電車時刻や迎えを待つ「すき間時間」を有効活用してもらい、自分を高めて欲しいと思います。今後とも、街なかでの滞在時間と消費を生み出すため、勉強や読書などに利用できる場所の拡充を進めていきます。 -
越中万葉かるたを使った万葉集を未来に受け継ぐ教育の推進
越中万葉かるたを使った万葉集を未来に受け継ぐ教育の推進越中万葉かるたは古城ライオンズクラブが45年前に制作されたもので、万葉集を愛する小中学生の子どもたちの初春恒例行事として、毎年越中万葉かるた大会を開催いただいています。大会のために練習を重ねてきた子どもたちには「大切にしている一首」があり、大会後も忘れることのできない、心に刻まれた歌になります。子どもたちがこれから先の人生、高岡市と自分を結ぶ万葉集として、大切にする一首があることは万葉集を次代に繋ぐためにも大変重要です。万葉集を守る大切なツールとして、もっと越中万葉かるたを身近に感じてもらえる遊び方はないか、百人一首の「ぼうずめくり」のような、新しい遊び方を検討し、老若男女が楽しめるものになることを目指し、越中万葉かるたの普及に努めて下さっている古城ライオンズクラブの皆さんに協力を呼びかけ、共に検討していきたいと思います。
-
君も億万長者になれる!子供向け起業家育成セミナーやワークショップの開催
君も億万長者になれる!
子供向け起業家育成セミナーやワークショップの開催昨今、社会課題をビジネスで解決していくという新しいビジネスモデルが注目されています。お金を稼ぐ方法として「物を作ったり、売ったりする」事は誰にでもイメージしやすいビジネスモデルですが、社会課題の解決など今は無いものを生み出す「ゼロイチ」ビジネスモデルは、実際に体験しないと分かりません。何を課題として捉え、解決のためのビジネスモデルを構築し、実践、対価を得るといったビジネス思考を育成していくためのセミナーやワークショップを開催し、子どもの頃からの起業家マインドの醸成に努め、将来、地域課題を今は無いビジネスで解決し稼ぐ、億万長者の可能性を秘めた起業家の卵を育んでいきます。
Key Policies