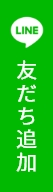Key Policy
人口減少対策 人口減少対策
これまでの実績

- 市独自の移住支援金制度により、転出者を上回る転入者があり、2年連続で社会増を達成。
- ふるさと納税の寄附額が5億円を突破。さらなる地域財源の確保に成功。
- 高岡スポーツコアに人工芝運動場を整備し、地域のスポーツ環境が大きく向上。
- ガバメントクラウドファンディングを古城公園再生プロジェクトで活用開始!市民のご寄附により、10年計画が倍速で進行。
- おとぎの森公園のカフェ誘致と駐車スペース増加による魅力向上。
- 城端線・氷見線の再構築計画が認定 法改正後で全国初。
- 高岡駅南北通路のストリートピアノ設置・ドラえもんポスト移設で賑わいを創出。
- 地域交通を複数地区で導入済み。
- 旧高岡共立銀行(赤レンガ建物)の活用決定⋯etc
今後すぐに始めていくこと
交流人口、移住定住人口の増加による社会増
未来を見据えて取り組むこと
健康寿命の延伸と出生率の向上による自然増
【実現のための具体策】

暮らしに潤いをもたらすまち(24策)
-
社会体育施設などによる誰もが楽しめるスポーツ環境の充実
社会体育施設などによる誰もが楽しめるスポーツ環境の充実学校再編に伴い、学校体育館の今後が課題となっています。比較的に新しいものもあれば、すでに耐久年数を超えている施設もあり、取り扱いはそれぞれで異なります。まずは「一律ではない」ことをご理解いただき、その上で今後の方針を決めていかなければなりません。市民の中には避難所や地域拠点としての活用といったアイディアを出していただく方もおられますが、既に耐久年数を超えている施設を残す事は次世代の負担となる可能性は避けられません。一方で、障がい者スポーツの振興やニュースポーツの普及など体育施設の利用ニーズが高いことも事実です。これまでの各学校による学校施設開放事業から社会体育施設に生まれ変わらせることで、利用料も適時適切にお預かりでき、持続可能な施設運営が可能になります。予約体制もオンライン化を進めるなど、誰もが楽しめるスポーツ環境の実現につなげていきます。
-
プロスポーツ誘致が可能に サブアリーナ建設から始める新総合体育館建設
プロスポーツ誘致が可能に
サブアリーナ建設から始める
新総合体育館建設高岡市総合体育館については、スポーツ愛好家やスポーツ競技団体の方々の長年の夢だと認識しています。一方で、人口減少に伴う「スポーツ人口の減少」や資材や人件費など「物価高騰の影響」が図り切れない中で、施設整備あり気で進めていくことは大変難しいのも現実です。結果、市民から「中途半端なものを作って…」と言われないためにも、既存施設の有効活用の観点を捨てるわけにはいきません。高岡市には竹平記念体育館という素晴らしい施設が民間によって建設され、高岡市に寄附されました。施設を寄附いただいたということはこの施設をいかに有効活用していくかが問われています。高岡市教育将来構想検討会議からプロスポーツ誘致や既存施設の有効活用などのご提案をいただき、検討を重ねた結果、将来の総合体育館の建設に向け着実に歩みを進めると共に、竹平記念体育館にサブアリーナを建設することを決めました。当然、既存施設の耐久年数もありますが、その際にはサブアリーナを単独で残し、社会体育施設として活用することはもとより、小矢部川周辺住民の水害等の避難所としても活用できるように、将来を見据えた計画を進めていきます。
-
高岡スポーツコアリフレッシュ事業の推進による目で見える新たな賑わい創出
高岡スポーツコアリフレッシュ事業の推進による目で見える新たな賑わい創出高岡スポーツコアは竣工から31年が経過し、老朽化した施設の対処に追われ、未来を描けていませんでした。私は高岡のスポーツにおける中核的な施設であれば、時代の変化も取り入れつつ、魅力を向上していかなければならないとの考えのもと、まずは本市にない施設である人工芝の運動場を造り、今年供用を迎えました。そこに人がいて、歓声が聞こえる屋外スポーツ場は、近くを行き交う人が目や耳で「賑わっているな」と感じてもらえる、はまさに賑わいの場です。人工芝フィールドに沢山の人と歓声が溢れることを願っています。今後は総合体育館の建設予定地である多目的広場の利活用やアーバンスポーツ導入等の可能性調査を実施していきます。
-
アーバンスポーツやニュースポーツの振興と拠点整備
アーバンスポーツやニュースポーツの振興と拠点整備若者を中心に人気のスケートボードにストリートバスケットボール等のアーバンスポーツ、老若男女問わず楽しめる富山発祥のクリングなどのニュースポーツの普及振興を目指し、拠点整備に向けた調査を開始すると共に、高岡駅北口交流広場の魅力向上策として、バスケットボールができる環境を整備するほか、スケートボードパークについてもニーズ調査やその運営方法を模索すべく仮設パークを整備します。一方で、新しい事を始めるには住民の理解を得ることも重要です。これらのスポーツを楽しむ方と協力し、地域への貢献についても考えていきたいと思います。
-
雨でも大丈夫!子どもたちが遊べる空間の創出「どこでもこども遊び場事業」
雨でも大丈夫!子どもたちが遊べる空間の創出「どこでもこども遊び場事業」「雨が降ると子どもを連れていく場所が少ない」このような声を多くいただきました。今年度、高岡市営業部提案事業として「どこでもこども遊び場事業」をスタートし、まずは市の遊休施設や屋内イベントで可動式遊具を設置し、市民のニーズや管理体制に関する調査を実施します。加えて、御旅屋セリオのこども広場をリフレッシュし、様々な取り組みを強化し、遊び場を増やすことで、「雨が降っても大丈夫」「雨でも遊べる」と子どもや保護者が楽しめるまちづくりを推進します。
-
次の20年へ おとぎの森公園魅力向上策の推進
次の20年へ おとぎの森公園魅力向上策の推進供用開始から25年が経過したおとぎの森公園。これまでのように単に修繕を繰り返すのではなく、より魅力を高めていく「アップグレード」を目指し「おとぎの森公園魅力向上化計画」を掲げました。最もニーズの高かった「カフェの誘致」「駐車スペースの増加」を今年実現できました。次は「水で遊ぶ空間の再構築」「誰もが安らげる場の造成」など、これからも市民に喜んでもらえる魅力向上策を継続的に進めて参ります。
-
市民の心のオアシス 古城公園セントラルパーク化(樹木管理行動計画推進)
市民の心のオアシス 古城公園セントラルパーク化(樹木管理行動計画推進)古城公園は市民の大切な憩いの場である一方、先人達から引き継いだ高岡の大切な史跡でもあります。これらをいかに共存共栄させていくのか。悩みましたが、まずは鬱蒼と生い茂った樹木を管理する事で、古城公園の史跡である所以を市民に目で見て共感してもらうことに取り組むことにしました。また、行政として進める工事に加え、古城公園に想い入れのある方々にご寄附をお願いするガバメントクラウドファンディングを本市としては初めて導入しました。これにより、年間の工事発注エリアが増大し、現在、計画は倍速で進んでいます。市民の心のオアシス、高岡市のセントラルパーク化を目指して、今後も着実に進めていきます。
-
古城公園を後世に繋ぐ市民の会発足・連携強化
古城公園を後世に繋ぐ市民の会発足・連携強化古城公園にはカラスやヒル、ブラックバスにアリゲーターガーと生き物に関して課題を多く持っています。行政として然るべき対応を取るものの、マンパワー不足は否めません。古城公園には長年、ボランティアでヒルの駆除にあたってくださっているご夫婦、カラスとの闘いを進める自治会、会社を休んででも外来種の駆除に参加してくださる方など、古城公園を大切に想い、行動して下さる多くの市民がおられます。口を出すだけ、文句を言うだけでなく行動を共にしてくださる皆さんのことを心強く思い、市長として感謝と敬意で一杯です。今後は皆さんに「古城公園を守る」という共通の立場を立って、引き続き古城公園を後世に繋ぐ活動にご尽力いただけるように、「(仮称)古城公園応援隊」を創設し、市から隊員任命を行い、より活動しやすい環境を作ります。
-
停まりたくなる駅を目指し、新高岡駅・周辺環境の充実
停まりたくなる駅を目指し、
新高岡駅・周辺環境の充実「定期便のかがやきが停まらない」「もっとJRに対して強く要望を」といったご意見を聞きます。要望だけで「かがやきが停まる」とのお考えであれば、残念ながら、そんなに甘い話ではありません。JR側からずれば、停めたはいいが、乗車が少なく、採算が合わなければ、それこそ二度と停まらない駅になってしまいます。冷静に受け止めなければなりません。まずは、かがやきが停まる条件を新高岡駅が満たしているのかが重要です。そのためには人が行き交い、乗車率も高く、人が降りたくなる駅にしていく必要があります。観光コンテンツの充実や駅周辺環境の整備を市独自に進めることはもとより、飛騨地方、能登地方と連携を強化し、飛越能の魅力向上策に努めてまいります。
-
「使う」「使える」「使いたくなる」鉄道へ 城端線氷見線の再構築計画推進
「使う」「使える」「使いたくなる」鉄道へ 城端線氷見線の再構築計画推進今任期中、一番の挑戦だったのが、城端線氷見線の今後について道筋を付けることでした。高岡市単独で進めることはできませんし、関係市がそれぞれの想いを持っておられ、その調整は困難を極めました。まずは、関係市の市長の想いを丁寧にお聞きし、いずれ市の主張も全て盛り込んで進む事はできないか、国会議員の先生方や知事から多大なお力添えをいただき、日本で初となる再構築計画に挑戦することとなりました。今後10年の計画をはっきりと示すことができたことは大きな第一歩です。今後は再構築計画にのっとり、JRやあいの風とやま鉄道を含め、関係の皆さんと密に協議を行い、それぞれの市、そして市民の願いが叶う鉄道を目指し、高岡市は鉄路を繋ぐ結束点としての責任を果たして参ります。
-
再構築計画と並行して駅周辺の次代のまちづくりを地域と共に検討
再構築計画と並行して駅周辺の次代のまちづくりを地域と共に検討城端線氷見線の再構築計画を推進することで鉄道の利便性は向上しますが、それに合わせてそれぞれの駅周辺のまちづくりも検討していかなければなりません。人口減少時代の中において大幅な乗降者数の増加は容易ではないものの、あいの風とやま鉄道高岡やぶなみ駅では新興住宅地が隣接したことにより、人口、乗降者数ともに大きく増加しました。このように駅周辺において、次代のまちづくりを進めることで、より持続性ある地域や鉄道へと進化します。公共交通とまちづくりを合わせて考える機運を醸成し、駅周辺の地域と共に検討していきます。
-
「待って、過ごして、楽しい」高岡駅進化計画の策定(南北通路改革)
「待って、過ごして、楽しい」高岡駅進化計画の策定(南北通路改革)高岡駅には地方駅としては珍しい京都駅と同じ幅の南北通路があります。南北通路の魅力を向上していくことは高岡駅の課題解決にも繋がります。一方で、鉄道の安全確保が最優先であり、鉄路の上を走る南北通路には様々な制限もあり、「できる事」「できない事」もありますが、それでも必ず「できる事」はあります。諦めるのではなく、できる事から始めればいい。これまで、駅の賑わい創出や電車の乗り換え時間の有効活用を目指し、ストリートピアノを設置したところ、大変多くの方にご利用をいただき、好評を得ました。また、ドラえもんポストを南北通路に移設し、新たな待ち合わせスポットとなりました。今後も南北通路全体のリデザインを目指し、関係機関との協議を重ね、「待って、過ごして、楽しい」高岡駅を目指して進化を続けていきます。
-
「景観も心意気も日本一の駅・雨晴」を目指す施策の推進
「景観も心意気も日本一の駅・雨晴」を目指す施策の推進世界に誇れる景観を持つ雨晴。観光列車「べるもんた」が走り、多くの観光客が訪れるのが氷見線雨晴駅です。レトロな雰囲気を活かしつつ、そこで暮らす人々が交流する観光スポットを目指し、まずは駅構内に展望デッキ「AMAHARASHI VIEW(仮称)」を設置し、通過せず、降りてもらえる駅環境の整備を進めています。今後は道の駅や周辺店舗とも連携を図りながら、まずは日本一の景観とおもてなしの駅を目指して、様々な取組みを進めていきます。
-
世界で一番美しいキャンプ場へ アウトドア施設誘致による官民連携事業の実施
世界で一番美しいキャンプ場へ
アウトドア施設誘致による官民連携事業の実施雨晴海岸を望むキャンプ場は人気のアウトドアスポットである一方、無料の施設であることから新たな投資が見込めず、現存維持に努めるに留まっています。県の施設ではありますが、ここを高岡の新たな賑わいの拠点とするために県と協議を続けてきました。また、高岡市が独自に行ったサウンディング調査では複数の民間企業が参画意欲を持っていることも分かっています。民間のノウハウで生まれ変わる雨晴キャンプ場。標高3,000ⅿ級の山々を海越しに見ることができる世界でも類を見ないアウトドア施設を売りに、雨晴、高岡市を世界に向けて発信します。
-
気軽に乗れる万葉線 乗車人数増加に向けた取組み加速
気軽に乗れる万葉線 乗車人数増加に向けた取組み加速万葉線は高岡市と射水市新湊地区を結ぶ市民の大切な公共交通です。一方で、人口減少や少子化の影響を大きく受けており、コロナ禍以降、乗降客の伸び悩みが続いています。鉄路は一度、廃止してしまうと二度と戻ることは無く、失ってからその大切さに気付いても取り返しがつきません。今こそ万葉線の価値を見直し、まちの財産として市民が認知し、乗ることが持続性を高める唯一の方法として受け止め、そのことを踏まえたまちづくり施策を集中して実施する必要があります。人が支える鉄道へ。万葉線乗車人数の増加を目指す取組みを加速していきます。
-
家から行きたい時に行きたいところへ 人と人をつなぐ市民協働型地域交通の強化
家から行きたい時に行きたいところへ 人と人をつなぐ市民協働型地域交通の強化鉄軌道や幹線バス路線の持続性を高め、人が行き交うまちを目指すためには、駅や行きたい場所をつなぐ交通形態が必要不可欠です。市長就任後、守山地区の「もりまる」、中田地区の「ノッカル」、野村地区の「のむたく」、木津地区の「ぐるりんバス」と、地域住民による地域のための新しい交通形態、市民協働型地域交通を導入し、高岡型のコミュニティ交通の確立を目指してきました。今後も駅へ、病院へ、買い物へ、地域住民の想いがつながる交通形態を各地域で導入すべく、地域の皆様との話し合いを進めて参ります。
-
街中が歩いて楽しいエリアに ウォーカブルシティ施策の検討
街中が歩いて楽しいエリアに ウォーカブルシティ施策の検討高岡駅周辺では民間資本によるホテルやマンション、有名旅館のレストラン事業の進出など新たなスポットが誕生しています。また、新型コロナが5類へ移行後、飲食店が中心となり、街中に活気も戻りつつあります。街中に更なる賑わいを生み出していくためには「中心市街地をみんなで盛り上げよう!」といった市民の行動変容が求められます。そのためには、商店街や事業者は「街中により魅力的な用事を作る」、市民は「用事+αの気持ちで街にでる」、行政は地域と一緒に「滞在できるまちづくりを進める」。中心市街地はカーボンニュートラルの先行地域であり、CO2排出の観点からも、車社会から歩いて楽しい街へ変容していく必要があります。それぞれがしっかりと役割を果たすことで、街中をもっと楽しいエリアに進化させます。
-
文化財・文化エリアの保存と利活用の推進
文化財・文化エリアの保存と
利活用の推進市長就任後、橘代議士のお力添えのもと、新田知事と共に取り組んだのが「勝興寺の国宝指定」でした。代議士や知事には文化庁長官への要望など、大変なご尽力をいただきました。その結果、令和4年12月に勝興寺が国宝指定を受けました。長年、国宝化に向け、ご尽力をいただいた全ての皆様に敬意を表すと共に、一つの市で2つの国宝建造物をお預かりするという重責に身震いしたことを覚えています。国宝は所在地の自治体が責任を持って保存していく必要があります。一方で、国宝を支える担い手の確保や育成、市民の国宝への理解促進など、未来に国宝を繋いでいくためには、保存に加え、「国宝の利活用」が重要となります。これは国宝だけに当てはまる事ではなく、文化財や文化エリアも同じだと考えています。「保存から利活用へ」歴史・文化都市高岡の新たな挑戦を推進して参ります。
-
国宝と出会うまち高岡 観光イメージ戦略の推進
国宝と出会うまち高岡
観光イメージ戦略の推進高岡駅から歩いて行ける所には国宝瑞龍寺が、また高岡駅から氷見線で伏木駅に降り立てば国宝勝興寺が。高岡はまさに国宝に出会える街です。しかし、国内外へはまだまだ浸透していないのも現実で、観光地を検討する際の候補に選ばれる街にならなければなりません。高岡の観光サイト「たかおか道しるべ」を昨年「高岡観光ナビ」へとリニューアル致しました。単にホームページの刷新ではなく、市民ライターによるローカルな情報発信や観光地めぐりのシミュレーションなど観光客視点での作りになっています。「伝えたいこと」ではなく、相手が「知りたいこと」を届けるなど、選んでもらえる観光地を目指し、観光戦略を持って、「国宝と出会えるまち高岡」の発信を推進していきます。
-
赤レンガ建物がホテルレストランへ 民間活力の導入による山町筋の新たな魅力創出
赤レンガ建物がホテルレストランへ 民間活力の導入による山町筋の新たな魅力創出高岡の中心部にある重要伝統的建造物群保存地区「高岡市山町筋」にある旧高岡共立銀行、通称、赤レンガ建物は県内唯一の大正時代の本格的な洋風建築です。利活用を巡っては、様々な考えがありますが、耐震工事に莫大な費用がかかること等から官民連携を模索してきました。プロポーザルの結果、優先交渉権者が決定し、いよいよ本格的な調整に入っていきます。この開発とプロジェクトにより山町筋が抱えた課題をいかに多く解決できる施設となるかを考えています。観光客からは「ホテルがない」「特別感のある食事をしたい」などの御意見をいただきました。また、赤レンガ建物の内覧会で市民の皆さまからは「外観を活かした民間施設を誘致しては」「素晴らしい内観を活かした活用を」とのご意見をいただいており、それらを精査していき、山町筋の新たなランドマークを誕生させていきます。
-
観光の必須立ち寄り場へ 高岡・雨晴の道の駅の機能強化と魅力向上策の展開
観光の必須立ち寄り場へ
高岡・雨晴の道の駅の機能強化と魅力向上策の展開高岡市の観光施設として「道の駅」は大きな役割を担っています。一方で、開業から年数が経ち、それぞれの施設が課題を抱えています。例えば、両施設に共通する課題の一つとして、観光客数が増加傾向にあるなかで、駐車台数が少ないという課題等があります。せっかく訪れたのに車が停められないから通り過ぎていく等の「もったいない」を無くすために、各施設の課題を洗い出し、機能強化と魅力向上策を実施し、稼ぐ観光を戦略的に進めていきます。
-
高岡御車山会館を年中行きたい場へと改革し、御車山祭りの魅力発信
高岡御車山会館を
年中行きたい場へと改革し
御車山祭りの魅力発信山町筋の観光施設、高岡御車山会館は御車山祭りの際には大勢の人で賑わう一方、一度訪れた方がまた来たいと思える仕掛けや普段から立ち寄れる施設になるという面からは改善すべき点もあります。これまでの運営を見直し、民間による指定管理者制度を導入し、民間のノウハウを生かし、「行きたくなる施設」へと進化するとともに、「お土産を買える場所が少ない」「気軽に立ち寄れる場所が欲しい」など、山町筋の課題解決に寄与できる施設を目指します。そして、私達が誇る高岡御車山祭りを世界に向け発信し、後世へ引き継いで参ります。
-
落語や舞台演劇など心に潤いを与える市民文化活動への支援強化
落語や舞台演劇など心に潤いを
与える市民文化活動への
支援強化コロナや震災で市民の心が疲弊する中、行政がいかなる支援をしようとも心の復興には限界があります。この間、私自身の心も落語や舞台演劇など市民の文化活動に何度も救われました。「市民の心に光を」文化活動には心を救う力があります。これまでも「どこでもステージ事業」や「ユニークベニューTAKAOKA」など新しい事業を通じて、文化活動を支援してきましたが、今後はより一層、自ら企画運営し市民に文化を届けようと頑張る文化人を応援し、市内至る所で笑いや感動が生まれる環境整備に力を注いで参ります。
-
市民会館跡地を屋外イベントのできる広場化等利活用策の検討推進
市民会館跡地を屋外イベントのできる広場化等利活用策の検討推進古城公園内の市民会館跡地に関しては、解体後、現在、埋蔵文化財の調査を行っています。史跡の上に建設してあったため、調査は必須であり、鋭意、調査を進めています。調査は文化庁監修の下、複数年かかる見通しですが、その後の利活用についても検討を進めていかなければなりません。史跡を傷つけ可能性のある工事はできませんが、史跡と公園機能を共有できる利活用策は必ずあります。例えば、屋外イベントが開催できるようなステージや緑地帯、平時は駐車場として活用できるといった複数の活用が可能な場所へと進化させていく事が重要です。文化庁に指導を仰ぎつつ、調査と利活用策の検討を進めていきます。
人口減少時代を生き抜くまち(13策)
-
目指すまちの姿を市民と共有する「シン総合戦略」の策定
目指すまちの姿を市民と共有する「シン総合戦略」の策定総合計画と合わせて策定する総合戦略は人口減少や地方創生に資する具体策を盛り込んだ戦略的計画でなければなりません。また、目指すまちの姿を具体的な数値を持ってお示しし、達成に向け、共に様々な事業を検討していく際に使用する計画になります。これまでの計画は国の方向性に合わせ、国の支援を受けるために必要な計画でした。石破総理のもと、地方に今一度光が当たる中、高岡市が「社会課題が山積しているまち」から「社会課題を先進的に解決していくまち」へ進化していく好機と受け止め、そのための戦略となる「シン高岡総合戦略(仮称)」を市民と共に策定します。
-
首都圏に拘らず全国どこからでも移住を支援する体制の強化
首都圏に拘らず全国どこからでも移住を支援する体制の強化これまで移住の支援については全国的に国の支援を受け、首都圏からの移住に限って支援が行われてきました。どこに住んでいようと高岡に引っ越したい、移住してみたいと考えて下さる人を増やすためには首都圏に限らず、県外であればどこから移住されても支援できる体制にすべきと考え、高岡市独自の移住支援金を設け、令和5年度の人口動態は「出ていく人」より「入ってくる人」が多い社会増となりました。今後も現在の支援メニューを精査、拡充し、高岡市に関心を持ってくださる方を増やしていきます。
-
UIJターンに継ぐ高岡型「O(循環)ターン」の推進
UIJターンに継ぐ高岡型
「O(循環)ターン」の推進Uターン、Iターン、Jターンと移住にはそれぞれ特徴がありますが、高岡市で生まれ育ち、その後、どこで暮らそうとも高岡市との縁は消えることが無いはずです。一方で、住民票を移されてしまうと行政との接点は無くなり、連絡を取ることも難しくなります。例えば、コロナ禍の中、行動制限によって外出もままならず、帰省できない市外の学生等に支援物資を送れないか検討した際、学生の住所や送付先を掴むこともできませんでした。今後、彼らに地元での就職を検討してもらうために企業情報を提供しようとしても今は手段がありません。そこで、厳正な個人情報の取扱いのもとで行うことを前提に、住民票を移す際に登録をしてもらう制度を作り、移住後も高岡市からの情報提供が可能な体制を検討します。それにより、全国どこにいても、どこで人生を過ごそうとも高岡市との縁を保ったまま暮らす事が可能になります。本市としても関係人口の把握ができ、両者にとってメリットが生まれます。いつ帰ってきてもいいし、帰って来なくても、ふるさとを応援し続けられる関係を構築します。英字で表現するならば途切れる事の無い「O」が適しており、繋がりを保ち、いつでも帰れるという意識を持って活躍してもらえる高岡型「Oターン」の意識醸成を図っていきます。
-
人口の社会増を目指した移住施策の推進
人口の社会増を目指した
移住施策の推進昨年度の高岡市は震災の影響から人口の流出が懸念されましたが、結果は社会増となりました。令和5年度はマンションなどの民間投資によって住環境が整った事もあり、中心市街地で社会増という明るい結果が出ました。この数字を一過性のものにせず、今後も高岡市に社会増の流れが続くように移住施策を充実させていかなければなりません。例えば「高岡市空き家・空き地情報バンク」と連動した形で、移住者が空き家を購入し、リフォームする際の助成を上乗せするなどこれまでの市民向けの施策を移住者向けにアップグレードしていく事も重要です。人口減少、少子高齢化社会においても、まちの担い手を確保していくため、移住者支援策を充実させて参ります。
-
人生の転換期「二十五歳の集い」など若者の選択を応援
人生の転換期「二十五歳の集い」など若者の選択を応援「これからの人生について考えるタイミングはいつ頃でしたか?」大学を卒業し、就職して数年たった頃、将来が見えてくるのではないかとの仮説を立て、25歳をターゲットに今後の人生について考えていただけるイベントを開催したいと思います。二十歳の集いから5年。同世代の仲間と集まり、結婚や転職、将来について考えたり、語り合ったり、新たな出会いを生み出します。また、担い手の確保を目指す地元企業にも参画いただき、担い手確保を目指し、「転職したくなる」「転職を検討してもらえる」企画を検討していきます。
-
押し付けるのではなく「結婚っていいな」と感じられる婚活支援
押し付けるのではなく「結婚っていいな」と感じられる婚活支援少子化対策の一つに、婚活支援があります。結婚という概念は時代によって大きく変わっており、私も学生に「結婚の何がいいのですか?」と聞かれ、ハッとした事がありました。何がいいのか…大切な人と過ごす時間や愛する子どもとの触れ合い。一方で、一人の時間が無くなり、将来や子育てにかかるお金の事も考えていかなければいけない。手に入るものと失うものがある事を受け止めなければなりませんが、それはいずれも経験したからこそわかる事です。「結婚っていいもの」と押し付けるのではなく、例えば既婚者の本音を飾らずに聞け、疑問をぶつける事ができる場の創出など、これから結婚を考える人が自然と結婚生活の両面を理解し、その上で「結婚っていいな」と感じてもらえる結婚支援策を展開していきます。
-
ふるさと教育の取り組み強化(17歳の決断)
ふるさと教育の取り組み強化(17歳の決断)富山県が実施している「14歳の挑戦」は子どもが社会体験するカリキュラムであり、中学生にとって社会との接点を持つ重要な機会です。14歳で幼少期に憧れた仕事や地域の産業を知り、実際に体感してみて、より具体性のある将来像を描く、そして18歳になり、進学や就職といった選択をしていかなければなりません。現状は残念ながら、進学を機に県外に出て、そのまま就職となり、戻ってはこないケースがほとんどです。高岡市が高校2年生を対象に行ったアンケート調査では、「高岡市に住み続けたいと思わない」と回答した22.8%の内、「やりたい仕事がない」と回答した人は14.5%を占めており、「働きたいと思える企業が無いと思っているから地元に住み続けたいと思えないと考えるのではないか」との推察ができます。そこで、「17歳の決断」と銘を打ち、進路選択の直前である高校2年生を対象に、地元の産業や魅力的な企業の存在、東京等首都圏と地元での生活による将来設計の差など、学生が進路を選択する上で事前に「知っておきたい事」「知っておくべき事」に応える場を創出し、正しく情報を持った上で進路の選択、決断をしてもらえるようにします。
-
こどもの夢応援企画の官民実施
こどもの夢応援企画の官民実施「高岡市をどんな街にしたいか」青臭い事を言いますが、「夢が叶う街にしたい」と答えています。小さい頃に抱いた夢を親だけではなく、あらゆる人が応援する環境を整えて、世界に例の無い「どこよりも夢を応援するまち」になりたいと真剣に思っています。七夕祭りで子どもたちの将来の夢を毎年見ていますし、私はよく子どもたちに夢を聞きます。その際、夢は「職業」ではなく、「何をしたいか」が夢であって欲しい。「職業」はその「夢を叶えるために必要なスキルや立場」と話しています。野球選手や医師といった「職業」ではなく、夢を与える人や命を救いたいといった「目的」を将来の夢として抱いてもらえるように取り組みます。子どもたちが将来の夢を語り、親や家族だけでなく、地域や企業、金融、教育、行政が真剣に考え応援する体制やそのプロジェクトを高岡市の新しい魅力にしていきたいと考えています。具体的には新市誕生20周年を機に、本気で夢が叶うまちを目指し、夢を応援するステークホルダーを集い「夢応援プロジェクト」を立ち上げます。プロジェクトでは「夢の現場を実際に体験」、「夢実現者から実現の方法を学ぶ」、「夢を叶える具体的な方法や課題を得る」、「夢に向かって進む」などのステージに応じた事業を興します。子どもが夢へのステップを駆け上がり、夢を叶えるその日まで、ステークホルダーが将来への投資として子どもたちの夢を連携して応援していきます。
-
学生団体との連携による若者主催のまちづくり
学生団体との連携による
若者主催のまちづくり高校生が高岡を想い、若者に選ばれるまちを目指そうと、新しい学生団体を立ち上げました。若者にまちづくりに参画して欲しいと考えていた私は地元の経営者や行政担当と学生団体を繋ぎ、事業のブラッシュアップに協力しています。今はまだ小さな活動だとしても、その志は高く、これからの時代に真に必要なシビックプライドそのものです。学生たちの活動を通じて、市民の皆さんにその心や志が波及してくように、共にまちづくりに挑戦し、学生に成功体験を積み上げてもらい、将来のまちづくりを託していけるよう支援して参ります。
-
学生の夢を叶えるためのファンド立ち上げ
学生の夢を叶えるための
ファンド立ち上げ夢を叶えるための進学や留学、習い事などにはお金がかかります。高校生が企業課題を解決するプロジェクトを提案する「キワプロ」で最優秀賞を取ったプロジェクトをより磨き、金融機関と共に、学生の夢を叶えるためにのみ引き出せるという特性を持った特別金利の定期預金事業を検討するほか、企業などから出資したファンドを立ち上げ、将来地元で活躍する可能性を秘めた学生に対し、投資支援事業を始めるための協議を進めていきます。
-
目指せ10億!ふるさと納税活用型まちづくり推進
目指せ10億!
ふるさと納税活用型まちづくり推進私が市議会議員になったおよそ10年前の本市のふるさと納税額は4000万円程度でした。人口が減る社会においては、まちに投資するための資金を外からも積極的に集めるべきと考え、「稼ぐ力の推進」を強く訴えてきました。市長就任後はふるさと納税を活用した資金集めに注力し、直近では5億円まで寄附額を伸ばすことができました。一方で、返礼品のメニュー拡大などのテクニックだけではなかなか10億円の壁は突破できないと全国の自治体から聞きます。そこで全国の自治体でふるさと納税のブラッシュアップに成功した実績を持つ方を招聘し、10億円を目指した壁の突破策をご教授いただくことを現在、検討しています。今よりも寄附額が倍増すれば、市民サービスへの政策投資額も増やせます。成功事例のノウハウを取り入れ、まずは10億円を目指して突き進みます。
-
課題解決策に直接支援 ガバメントクラウドファンディングの事業拡大
課題解決策に直接支援
ガバメントクラウドファンディングの事業拡大ガバメントクラウドファンディングとは、自治体が課題解決したい事業を設定し、ふるさと納税の枠組みを活用して、事業に必要な予算について広く寄附を集い、実施するものです。古城公園で実施している再生プロジェクトでは市民からの寄附により、10年の計画が現在は倍速で進んでいます。この制度をさらに活用し、地域課題解決に向けて該当となるプロジェクトを多数立ち上げ、それぞれの事業を広く発信し、寄附金を集い、時間のかかる事業をより短期間で仕上げれるよう知恵を絞って取り組みます。
-
高岡応援市民認定制度などで交流人口の拡大
高岡応援市民認定制度などで
交流人口の拡大人口減少時代にあって、定住・関係・交流人口の拡大は地域の持続性を高める上で重要です。特に外から高岡市を応援してくださる方を増やすことは、ふるさと納税や観光交流など稼ぐ力の推進に直結します。面白い制度は口コミで広がるため、関係人口や交流人口を増やす尖った制度を検討すべきと考えます。全国的にふるさと納税は、肉や魚など日常的で使用できる返礼品を持つ自治体に寄附が集まった時代から、「寄附金の使い道の明確化」や「地元でしかできない体験型の返礼品」を持つ自治体に注目が集まるなど変化が見られます。その先に向けて、例えばメタバース(仮想空間)上に架空のまち(自治会)を立ち上げ、仮想住民票を持ってもらう応援市民制度やふるさと納税の返礼品に「(仮称)認定!高岡応援市民」を加え、高岡市にお越しの際に飲食店や観光地で割引などのサービスを受けられる返礼品など、交流人口の拡大に向け様々な事業を展開します。
Key Policies