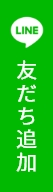Key Policy
誰もが住みやすいまちへ 誰もが住みやすいまちへ
これまでの実績
- 富山県内唯一の脱炭素先行地域に指定され、国の支援を受け環境と経済が両立するまちづくりを推進
- ヤングケアラー支援を強化し、ガイドライン策定やヘルパー派遣制度を新たに実現
- 能登地震を踏まえ、水道管の耐震化を前倒しで実施し、インフラ強靭化を推進
- 富山・射水・高岡3市で消防艇を共同保有し、海上の災害対応力を強化
- 能越自動車道福岡PAのIC化が進行中で、R10年度供用開始を目指し地域活性化を推進
- 空き家対策を独自推進し、解体助成や事前支援制度を導入して住環境を改善⋯etc
今後すぐに始めていくこと
今の場所から一歩前へ 挑戦できる環境整備
未来を見据えて取り組むこと
ヒト・モノ・コト 全てが循環する社会の構築
【実現のための具体策】

いのちと暮らしを豊かにするまち(13策)
-
アルミからはじまる循環経済型イノベーション都市の実現
アルミからはじまる循環経済型イノベーション都市の実現令和5年10月、高岡市に完成した富山大学先進アルミニウム国際研究センターでは再生アルミの研究を行い、これまで輸入に依存していたアルミについて、廃アルミを再生させ、資源循環による高付加価値産業の確立を産学官民で進めています。「アルミ缶やアルミ建材は廃棄するのではなく再生する」この意識醸成の鍵は市民です。富山大学と連携し、リサイクルアルミに対する意識の醸成を図ってまいります。
-
まちに新しい価値を 歴史・文化に次ぐ環境教育推進の街へ
まちに新しい価値を 歴史・文化に次ぐ環境教育推進の街へカーボンニュートラルを進める中で、中心市街地に新しい価値を創出できる可能性を感じています。カーボンニュートラルの見える化(ショールーム化)を進める事で、高岡市が環境を学ぶ場になり、遠足や校外学習、修学旅行など学ぶ事を目的とした学校行事の誘致が図れると考えました。先人達から引き継いだ歴史・文化の教育の場に加え、新たに環境教育の場として、内外からの人を呼び込み、まちの新たな価値を生み出していきます。
-
「ゴミなんて一つもない、全てが資源!」サーキュラーエコノミーの確立
「ゴミなんて一つもない、全てが資源!」サーキュラーエコノミーの確立高岡市にとってアルミは循環可能な資源であり、他市にとってはゴミでも高岡市にとっては資源です。地方自治体共通の課題にごみ処理があります。高岡市では他市のゴミ問題を救いつつ、自分たちの街に資源を取り込み、まちの力を高めることができます。この考えが広く波及していく事で、それぞれの地域の得意とする産業構造を活かした資源循環が各地に生まれ、プラスティックでもスチールなどでもこれまで捨てていたものを資源として回収し、地方を行き来する。サーキュラーエコノミーの確立は地方課題や産業課題を解決する起爆剤になります。合言葉は「ゴミは資源!!」です。
-
障がいの有無に関わらず豊かに暮らせる「やさしいまち」の創造
障がいの有無に関わらず豊かに暮らせる「やさしいまち」の創造人は一人では生きていけません。誰もが分かっている事なのに、いざ行動へとは結び付かない方も多いのではないかと思います。多種多様な人が同じ所で暮らしていることや支え合って生きていかなければいけないことを、また自分自身が支える側から支えらえる側にいつなるか分からないことを受け止め、「大丈夫ですか?」「手伝いましょうか?」「できることはありますか?」と意志を表現し、気持ちや意志を受け止めた側も遠慮せず「助けてください」「困っています」と表現できる「やさしいまち」を目指して、相手の考えや立場、状況を理解することができる取り組みを進めていきます。
-
農福連携のその次へ 高岡型商福連携推進
農福連携のその次へ 高岡型商福連携推進高岡市では働き手の確保に困られている農家と働く機会を求めておられる障がい者をつなぐ農福連携に力を入れてきました。農家の繁忙期を作物ごとに考え、年間を通した仕事になるようにすることで障がい者に定期収入が生まれる仕組み作りを進めています。一方で、働き手の確保に悩んでいる業界は増えています。互いに「できる事」「できない事」を理解し、できる事から始めてみる。まずはどんな事ができるのかを知ってもらうために、御旅屋人マーケットなどの街中イベントに参画される商業の方々からアルバイトで働く機会をご提供いただくところから始め、障がい者への理解を進めることで、高岡型の商福連携を推進していきます。
-
きずな発達支援センターの充実
きずな発達支援センターの充実こどもの発達障害は増加の一途であり、きずな発達支援センターは高岡市の施設ではあるものの、こどもの発達に悩む富山県重の方々の支えになっています。県も「こどもの発達支援に関する県西部の拠点」との認識を示している一方、その運営は予算や医師の確保等、難しい舵取りが求められています。きずな発達支援センターは高岡市民の大切な「こどもまんなか」事業であり、今後もその責務を果していくために、課題解決を急ぐ必要があります。運営支援のあり方について、ご利用いただいている他市とも議論を進め、きずな発達支援センターの持続可能な運営について検討を進めていきます。
-
危険空き家を防げ! 空き家になる前に対策を検討できる独自施策の展開
危険空き家を防げ! 空き家になる前に対策を検討できる独自施策の展開人口減少の進行にあり、全国各地で空き家問題が起きています。高岡市では独自の対策として、空き家解体後の固定資産税の負担増に対する助成制度や危険空き家になる前に地域で対処できるようにするための支援制度の導入など、先進的に取り組んできました。空き家増加の流れに歯止めをかけるべく、今後も全国の取り組みを参考にしつつ、今住んでいる方が責任を持って、今後について事前に検討できる対策や空き家を貸し出す際に行う修理や整理について補助する制の新設など、現状を打破する施策を打ち出していきます。
-
ヤングケアラーを見つけて守る 子供からのヘルプサインが届く環境整備
ヤングケアラーを見つけて守る
子供からのヘルプサインが届く環境整備ヤングケアラーとは家族の介護や日常生活上の世話を過度に行っていると認められる18歳以下の子供を指します。ヤングケアラーを取り巻く課題として、発見が難しい事が挙げられます。第三者が発見する体制を整備する事も大ですが、ヤングケアラー自身がヤングケアラーである自覚を持ち、支援を求める事ができる環境整備が重要です。ワンチーム推進本部でもヤングケアラーへの支援について協議し、これまでに支援ガイドラインの策定やヘルパーの派遣事業等が実現しました。今後も県や他市町村と連携し、子どもからのヘルプサインを受け取り、発見し、必要な支援策を届ける事ができる環境を整備します。
-
市民病院改革と地域交通課題の同時解決策、市民病院行き地域バスの運行支援
市民病院改革と地域交通課題の同時解決策、市民病院行き地域バスの運行支援「患者数を増やしたい」市民病院と「病院へ行きたい、通いたい」患者や地域を結ぶため、通院ニーズのある地域と市民病院間を走る地域バスの導入を検討する地域に対し、通常の市民協働型地域交通への支援策に加えて、補助率の嵩上げなどを検討するとともに、病院側ではバスの運行日に合わせた地域毎の優先予約制度を検討し、両者の課題解決を目指します。
-
「私たちの市民病院」へ 市民が応援してくれる市民病院改革
「私たちの市民病院」へ 市民が応援してくれる市民病院改革新型コロナウィルスが感染症5類へ移行し、感染対策に追われた病院も通常時に戻りつつある中、これまでくすぶっていた課題が顕在化しました。医師を始めとした医療従事者の確保、医師の働き方改革など病院を取り巻く環境は人口減少時代において大変難しく厳しい状況です。そのような中にあっても、市民の命を守る拠点として、市民病院はその責務を果たさなければなりません。そのためには市民が市民病院を自分たちの病院として捉え、行きたい病院へと進化しなければなりません。現在、市民代表による懇話会を開催し、未来に必要とされる病院の在り方をご検討いただいています。これらの意見を参考に市民病院の改革に挑みます。
-
受けたい医療が持続的に提供される高岡医療圏の構築
受けたい医療が持続的に提供される高岡医療圏の構築高岡医療圏には高岡市内4つの公的病院に加え、射水、氷見にも公的病院があります。公的病院の経営環境はいずれも厳しく、今後の在り方について病院経営や住民への医療サービス維持の視点等から議論が必要です。高岡医療圏の持続性をいかに高め、圏域住民の命を守っていくのか、国や県の力を借りて、再構築していきます。各病院による医療サービスの提供から役割分担を進め、それぞれの担いを全うすることでなせる面的医療サービスへ進化していかなければなりません。また、医療を現行の圏域だけで捉えるのではなく、さらに大きなエリアとして捉え検討していきます。
-
富山県内唯一の脱炭素先行地域としてのリーディング事業の実施
富山県内唯一の脱炭素先行地域としてのリーディング事業の実施高岡市は令和5年11月に環境省から脱炭素先行地域に指定を受けました。現在、富山県内では唯一であり、資源循環モデルとしては全国初の認定です。これにより、本市が先行地域で進める施策に関しては国からの強力な支援が受けられるため、単独財源で進める何倍もの速度でカーボンニュートラルを推し進める事が可能です。日本初の資源循環を高岡市から。市民や企業の皆さんと挑戦し、まずは再生アルミの資源循環をリーディング事業として、より高付加価値の付いたまちづくりを進めます。
-
地域も暮らしも豊かになるカーボンニュートラルの推進
地域も暮らしも豊かになるカーボンニュートラルの推進カーボンニュートラルの実現には市民の参画が不可欠です。しかし、今なおどこか他人事の感が否めません。次の時代に豊かな自然環境を残す事は今を生きる私たちの責任です。一人一人が責任を持って、自分にできる事を実践する。市民が動き、経済が躍進し、環境が保たれる。実感を持って、地域も暮らしも豊かになる社会の実現のためにも、市民の参画を強く呼びかけ、市民全員で完成する高岡型のカーボンニュートラルを目指します。
市民の命と暮らしを守るまち(13策)
-
通学路交通安全プログラムの着実な推進
通学路交通安全プログラムの着実な推進子ども達が毎日通る通学路にはまだまだ危険が沢山あります。この危険を国と共に解消していく事業が「通学路交通安全プログラム」です。各地域では関係者にご尽力をいただき、毎年の進捗確認や新たな危険ポイントの洗い出しをお願いしています。新興住宅地など子どもが集中する地区の移り変わりやこどもまんなか意識の醸成に伴い、小学校毎の要望も毎年増えています。今後も国と連携し、安全対策の早期完了を目指します。
-
保育園や幼稚園などの周辺安全環境整備の促進
保育園や幼稚園などの周辺安全環境整備の促進通学路交通安全プログラムは小学校の通学路が主たる対象であり、保育園や幼稚園の園舎周りは対象となっていませんでした。そこで高岡市単独の事業として、保育園や幼稚園などの周辺安全環境整備事業を立ち上げ、これまで3年間に渡り、事業を進めてきました。中には「10数年の地域課題だった道路改善が『地域要望に子ども目線を加える」事で前へ進んだ」との声もいただいており、地域要望に子どもの視点を加える事で優先順位を上げるという「こどもまんなか施策」の形が現れたものもあります。今後も子どもたちの生活環境の向上を未来への投資と位置付け、事業を着実に進めて参ります。
-
能越自動車道福岡パーキングエリアのインターチェンジ化
能越自動車道福岡パーキングエリアのインターチェンジ化福岡パーキングエリア内にインターチェンジを設け、周辺住民や企業、観光客の交通利便性を高めます。これは合併時に旧福岡町よりお預かりしていた案件であり、合併20周年を機に大きく動き出します。目標供用開始時期を令和10年度とし、地元のご協力を得て、今後は埋蔵文化財調査や設計等を進めていきます。
-
強い高岡に必要不可欠な消防体制の強化と拠点整備
強い高岡に必要不可欠な
消防体制の強化と拠点整備震災で分かった事の一つに災害の最前線に職員を送り出すためには、その拠点を担う体制と施設が強固でなければならないということがあります。現在進めている新消防庁舎の建て替えを着実に進めることで災害時の拠点を整備し、市役所の新庁舎についての検討を進める間の有事の際には消防庁舎を災害対策の拠点とできるようにします。また、有事からこのまちを救えるのは自分たちだという強い責任感を持った消防となるべく、職員倫理観の向上、資質向上にも尽力致します。
-
消防艇の3市共同保有による機能性と機動力の強化
消防艇の3市共同保有による
機能性と機動力の強化高岡市は令和3年4月に氷見市と消防の広域化を行い、高岡市と氷見市を所管する高岡市消防本部が立ち上がり、より強い消防体制が構築されました。この効果をより拡げるため、次に取り組んだのが、消防艇の共同保有です。これまで富山市、高岡市がそれぞれ保有していた消防艇の更新時期を見据え、富山市、射水市、高岡市で消防艇の共同保有について話し合いを進めてきました。両市の市長の理解を得て、協定を結ぶに至りました。共同保有する新しい消防艇はスピードやパワー等のスペックも大幅に上がりますし、コストも大幅に抑えることができるなど、3市に大きなメリットが生まれます。今後は設計、建造へと歩みを着実に進めていきます。
-
海難事故に備える水上バイクなど最新鋭資器材の充実
海難事故に備える水上バイクなど最新鋭資器材の充実近年、マリンレジャーも多様化しており、様々な海難事故にも備えなければなりません。消防艇の共有保有を進める一方で、高岡市としては様々なケースを想定した備えを強化していくことも重要です。伏木海上保安庁との連携を強化するとともに、臨機応変に機動的な活動が可能になる水上バイクを配備するなど、最新鋭の資器材を導入していくことで、市民の命を守る体制の強化を図ります。
-
消防団が自らの意志と判断で活動できる環境整備
消防団が自らの意志と判断で
活動できる環境整備私も元消防団員です。令和6年能登半島地震の際には消防団員から「自らの判断で動くことができず、悔しい想いをした」と聞かせてもらうことがありました。どうすれば指示をいち早く出し、取るべき行動を各団員が判断できるようになるのか。消防本部とも協議を重ねつつ、新消防団長のもと、より強い消防団を目指し、様々な改革に取り組んでいきます。
-
消防団施設や装備の充実等による強い消防団の実現
消防団施設や装備の充実等に
よる強い消防団の実現消防団の拠点となる施設には老朽化が著しい施設や迅速な出動に適していない施設もあります。拠点施設の更新を着実に進めるとともに、分団に配備された資器材の更新がおくれているものや分団によって装備品に差があるもの等を精査し、それぞれ更新を図っていくことで、各分団の消防力の向上に努めていきます。
-
ひねれば「出る・流れる」の当たり前の強化・推進
ひねれば「出る・流れる」の
当たり前の強化・推進令和6年能登半島地震ではおよそ4000戸が断水しましたが、管工事業協同組合の皆さんにご尽力をいただき、本市では発災から5日間で断水を解消する事ができました。正月返上で作業に当たってくださった事業者の皆様には心から感謝と敬意を表すると共に、改めて、人の力の重要性を感じた事案でもあります。一方で、ひねれば「出る・流れる」の当たり前が一瞬で奪われた事を忘れてはいけません。今後もいつ来るか分からない有事に備え、当たり前の強化・推進に努めます。
-
老朽管路の耐震化工事のできる限りの前倒し
老朽管路の耐震化工事のできる限りの前倒し令和6年能登半島地震において、本市が早期の断水解消ができた背景には管路の耐震化があります。特に被害が広域にわたった伏木地区では全市の耐震化率が41.2%に対して、伏木地区が84.8%と高かったことから、被害が一定程度抑えられたと捉えています。この経験からも、強い高岡の構築のため、管路の耐震化を全市的に進めていく必要があります。復旧・復興の状況を見極めつつ、できる限りの前倒し工事を進めて参ります。
-
持続可能な水道事業へ 周辺市との連携強化と未来を見据えた議論の開始
持続可能な水道事業へ 周辺市との連携強化と未来を見据えた議論の開始人口減少時代において、全国各地で水道の広域化が進んでいます。これまで高岡市は単独で運営してきましたが、今後は20年30年先を見据え、広域化を視野に入れていかなければならないと考えています。まずは隣接市と様々な可能性の検討を行うとともに、できるものから共同で行ってみるなど、一つ一つの実績を積み上げることで連携を強化し、その先の未来向けての議論を始めていきます。
-
上下水道ビジョンの着実な進行と時代に応じたブラッシュアップ
上下水道ビジョンの着実な進行と時代に応じたブラッシュアップ高岡市では上下水道ビジョンで定めた計画を着実に推進していますが、今回の震災や想定を上回る速度で進む人口減少時代を見据え、早めるべきは早め、違う方法での改善が見込めるものは積極的に検討するなど、時代に応じた見直しを進めて参ります。
-
国土交通省への事業移管後も安定した予算確保に向け積極的な要望活動
国土交通省への事業移管後も安定した予算確保に向け積極的な要望活動上水道事業は国の所管がこれまでの厚生労働省から国土交通省へ移管され、上下水道ともに国土交通省が所管することになりました。今後は道路や橋などのインフラと同等の扱いとなり、サービスの側面だけでなく、国土強靭化の一環として上下水道の整備・運営を捉えなければなりません。被災地の首長として、一日も早い復旧のためにも耐震化の重要性を国土交通省に強く訴え、上下水道事業に関する安定した予算確保を目指し、国会議員の方々や県のお力もお借りして、要望の実現に努めて参ります。
Key Policies