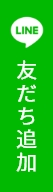Key Policy
誰にもやさしいまち高岡 誰にもやさしいまち高岡
これまでの実績
- きずな発達支援センターを県西部の拠点として充実し、発達支援を強化
- 高岡農林振興センター管内の野生鳥獣害対策
- 市長ホットラインを庁舎1Fに設置。市民の声を直接市長へ!
- 新婚世帯の住居取得支援事業スタート
- 産後ヘルパー派遣事業の拡充
- 移住コンシェルジュ、高岡ウェルカム移住支援で社会増を実現⋯etc
今後すぐに始めていくこと
現状や課題を正しく理解し助け合えるまちへ
未来を見据えて取り組むこと
誰もが等しく支え合う優しい心が溢れるまちへ
【実現のための具体策】

安心して衣・食・住を送れるまち(9策)
-
高岡産農作物の需要創出・生産拡大
高岡産農作物の需要創出・生産拡大市民の皆さんには高岡市産の一押し農作物はありますか?高岡市には魅力的な農作物が多数あります。戸出地区のトウモロコシやアスパラガス、木津地区の大根やカブ、国吉地区のリンゴやモモ、立野地区のユウカメロンなど個人的に収穫時期を楽しみにしている農作物も沢山あります。市民お一人お一人が「推し」の農作物を持ち、農家に代わって農作物をPRする「発信」と「消費」を同時に行うことで需要が拡大し、農家は必要とされる分量を見極めながら、生産を拡大していく。農業を取り巻く好循環の創出には消費者の行動が欠かせません。生産者と消費者が意見を交わす場を設けるなど、高岡市の食料自給率を高める市民行動を促し、高岡市の大切な農業を守っていきます。
-
コメの可能性拡大事業の展開(米粉、バイオマスプラスチック)
コメの可能性拡大事業の展開(米粉、バイオマスプラスチック)高岡市の農業の大半は水稲です。コメの需要が減少傾向の中、持続性ある農家を増やすためには、米農家の所得を増やさなければなりません。国の生産調整で減反した田んぼを有効活用すべく、これまで葉物野菜などへの転作を推奨し支援してきました。一方で、農家からは「米作はできても今から園芸に切り替えるのは厳しい」との声もいただいており、水稲で培った技術や機械を使って、需要のあるものを生産できないか検討して参りました。そこで、グルテンフリーという食文化が広がる中で需要の拡大が見込まれる「米粉」としての利用や石油原料のプラスチックに代わる新しい資源として注目が集まる「バイオマスプラスチック」としての活用など、コメの新しい販路開拓に取り組みます。これらは何れも米であり、水稲農家が培ってきた技術や所有する機械を活かすことができるため、新たな投資が少なく始めることができます。まずは始めるところから。実証実験をスタートさせ、需要と供給を図りながら、生産を拡大し、コメの可能性を拡大していきます。
-
農家の所得が向上し、新たな担い手確保につなげる農業の魅力向上策の展開
農家の所得が向上し、新たな担い手確保につなげる農業の魅力向上策の展開農家の所得が上がることは農業の魅力が高まり、新たな担い手を生み出すことにも繋がります。農業が意義深いものであっても稼げない産業のままでは、どれだけ呼びかけてもなかなか就労には繋がりません。仕事のやりがいに加え、豊かな生活をイメージできるものにする事が担い手確保に向けた鍵だと考え、高岡市の農業の中でも若手就農者が中心になって、年々生産拡大し、売り上げを伸ばしているチューリップの切り花農家の取組みなどの明るい話題を発信し、新たな担い手の確保に向けた施策を展開し、魅力向上を図ります。
-
できることをシェアして稼ぐ 二兎を得る農福連携の推進
できることをシェアして稼ぐ 二兎を得る農福連携の推進担い手不足に悩む農家と働き先の確保に翻弄する障がい者就業支援関係者を結び、互いにウィンウィンの関係を構築すべく、農福連携の強化に努めてきました。マッチング会では互いの抱える課題について共有するなど、進展はあるものの、まだまだ課題も多く、その解決に向けて取り組みを強化していかなければなりません。例えば、単独の農家では年間を通しての仕事の発注が難しいのであれば、生産品目の違う農家が複数で、収穫時期や作業を1つのスケジュールに落とし込み、一年間を通して作業の見える化を進める等の取組みもマッチングには効果的です。農家や事業者とアイディアを出し合い、より効果的な連携が実現するよう推進していきます。
-
山林などの自然環境の適正管理と資源の有効活用
山林などの自然環境の
適正管理と資源の有効活用山林は先人から受け継いだ大切な自然であり、エネルギーが見直される中、資源の宝庫としてもその活用が求められています。一方で、行政が単独で管理や活用できるものでもなく、所有者や森林組合、バイオマス事業者などとの連携の上、適正な管理や有効活用策の模索を続けていかなければなりません。「ボトルネック(課題)は何なのか、何を変えることで、山林に循環を生み出せるのか」を考え、助成や支援制度を見直し、適正な管理と資源の活用を行うなど、次の時代にしっかりと引き継ぐことができる山林の在り方を検討していきます。
-
山林所有者と林業・バイオマス業者をつなぐ里山保全事業の展開
山林所有者と林業・バイオマス業者をつなぐ里山保全事業の展開里山を適正に維持管理していくためには、山林所有者の意志が重要です。近年は相続などにより、山林所有者の意識にも変化があり、「何とかしたい」「手放したい」との思いをお持ちの所有者から相談をいただきます。一方で、自然エネルギーへの関心が高まる中、バイオマスとしての樹木活用のため、事業者が山林を必要としているケースもあります。木を切るだけでなく、植え替えを行い、山林の手入れも合わせて行っていく。土地の売り買いのためではなく、里山の保全を意識した事業として、関係者間を繋ぐ保全事業を協議していきます。
-
古城公園や散居村地区の剪定枝の回収と資源循環化の推進
古城公園や散居村地区の剪定枝の回収と資源循環化の推進散居村地区の屋敷林をお持ちの市民から高齢化が進む中、福岡町のストックヤードが無くなり、剪定枝の処理にかかる時間と労力について支援して欲しいとの要望があります。高岡市では昨年、散居村地区において臨時の集積場を設けて、剪定枝の回収を行いました。実証実験として行ったため、待ち時間や場所などの課題を抽出する事ができ、今後は開催時期や場所などを地域と協議し、より効果的な回収方法での実施を目指します。また、回収した剪定枝については資源化を目指し、民間企業による利活用を含め、推進していきます。
-
農業センターを有効活用し6次産業化を目指した社会実装実験
農業センターを有効活用し6次産業化を目指した社会実装実験稼げる農業の創出のため、市の農業センターの指定管理者制度を見直し、飲食店などを経営する民間企業に運営を任せました。稼ぐためにも、一次産業から二次・三次産業を取り込む六次産業化は重要な観点であり、そこには民間のノウハウが必要と考えており、今後、指定管理者とともに、六次産業化を目指す農業経営者が様々な事に挑戦できる農業センターを目指すと共に、挑戦される農家や事業者を支援できる体制を強化します。
-
先進例を取り入れたカラス、イノシシ、クマなどの有害鳥獣対策の強化
先進例を取り入れたカラス、イノシシ、クマなどの有害鳥獣対策の強化これまでの任期で有害鳥獣対策として、「カラス」には檻の増設や特殊な光線や音波による対策や年間を通した兵糧作戦を、「イノシシ」には地域と共に電気柵の延長や耕作放棄地の防止・解消策を、「クマ」にはAIカメラによる出没情報のデジタル化など、それぞれ対策を講じてきました。一定の効果は出ていますが、自然との闘いに終わりはありません。今後も全国各地で取り組んでいる効果的な最先端の対策を導入し、有害鳥獣との闘いを続けていきます。
Key Policies