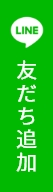Key Policy
未来につなぐまちづくり 未来につなぐまちづくり
これまでの実績
- 中心市街地の年間開業数が過去最大を記録!空き店舗活用でまちなかに新風
- 起業支援拠点「TASU」をオープンし、誰でも挑戦できる創業環境を整備
- 市債残高を着実に減少させ「子どもに借金を残さない」財政健全化を実現
- 「どこでも市役所」で18サービス展開中!スマホで手続き完結の利便性向上
- 「書かない窓口」を開始し、待ち時間短縮と手続き簡素化で市民サービス向上
- 伝統産業の担い手確保でコーディネーター育成開始!高岡銅器・漆器の技術継承
- 市内工業団地が完売!新規造成手続きを進め、高岡経済を牽引する企業誘致を推進⋯etc
今後すぐに始めていくこと
次の世代につけを回さない行財政改革の推進
未来を見据えて取り組むこと
強くて弾力性のある財源構造でのバトンタッチ
【実現のための具体策】
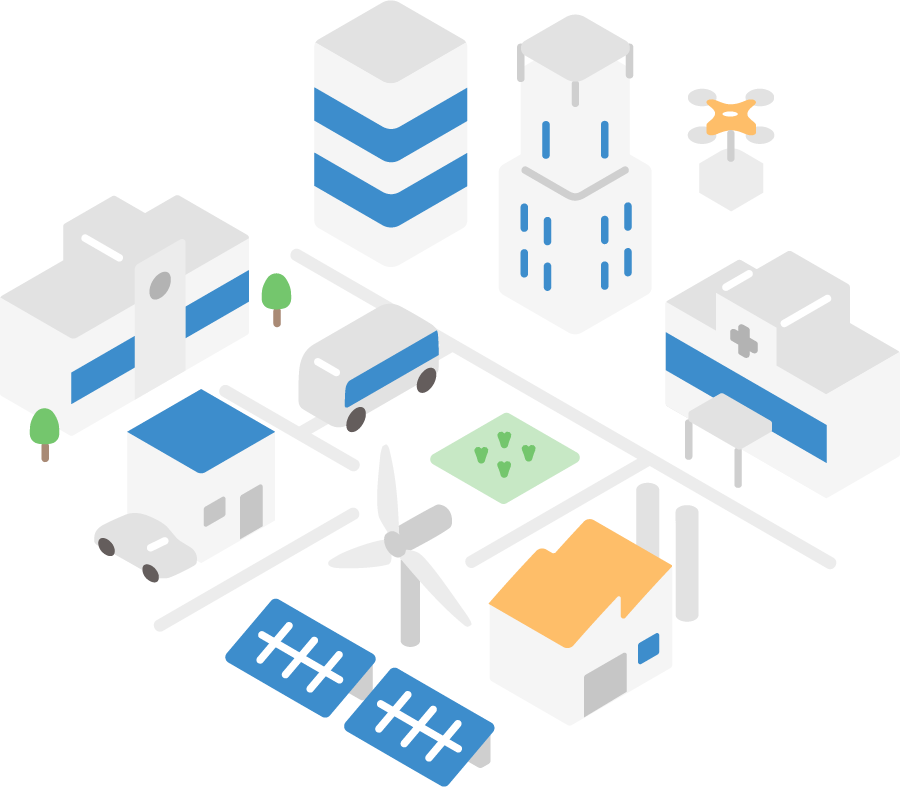
経済が先頭に立ったまち(14策)
-
再生アルミの循環推進による高付加価値アルミ産業の確立
再生アルミの循環推進による
高付加価値アルミ産業の確立アルミをはじめとした軽金属産業が本市の経済をけん引してきました。軽金属産業が未来に向けて経済成長を続けるためには、環境配慮型社会において高付加価値商品を生んでいく必要を感じています。アルミの地金はほぼ100%輸入に依存しています。一方で、国内では廃棄されるアルミも大量に存在しています。この廃棄アルミを再生し、再生地金として再利用するアルミの循環を本市で生み出すことで、環境にも配慮した産業として新たな付加価値を生み出すことが可能になります。富山大学の研究と民間の技術を結集し、市民生活で出た廃アルミからスタートする。いずれは国内中の廃アルミが本市に集まる施策を展開することで、高岡市はアルミ資源のまちへと変貌します。
-
新規工業団地の早期完成と企業誘致の推進
新規工業団地の早期完成と
企業誘致の推進現在、市内全ての工業団地において区画は完売しており、新たな工業団地の造成に向け、ニーズ調査や市街化区域の編入にかかる県への手続きを進めてきました。県からの許可を得た後は、速やかに工業団地の早期完成を目指して進めなればなりません。一方で、この間、進出意欲などの企業ヒアリングをしてきており、造成に向けた工事と並行して、進出に意欲ある企業に対し、造成スケジュールをお示しするなど、具体的な営業活動に入っていきます。本市の目指す「強い経済」を牽引してくれるような企業が本市を選んでいただけるよう企業誘致を推進して参ります。
-
誰もが起業家になれるまち スタートアップ高岡の挑戦加速
誰もが起業家になれるまち
スタートアップ高岡の挑戦加速市長就任後、誰でも挑戦できる環境作りの一環として御旅屋セリオ内にスタートアップ支援施設「TASU」をオープンしました。相談件数やセミナー数は当初の予定を大きく上回り、新しい高岡市の公共施設の顔となりつつあります。また市民には誰でも気軽に起業・創業に挑戦できるという意識が浸透し、実際に起業する方が増えてきています。今後は全国各地のスタートアップ施設とTASUを結び、域外を超えて、新たなビジネス交流の創出に向け、機能を強化するなど、より市民の皆さんが挑戦しやすい環境整備を加速していきます。
-
空き家・空き店舗を活用した家賃補助制度の導入など創業支援策の推進
空き家・空き店舗を活用した
家賃補助制度の導入など
創業支援策の推進空き家・空き店舗をどの様に活用するかは往年の課題になっています。民泊施設や飲食店、子どもたちの集う場などへの転用は全市的に少しずつ増えつつあるものの、更なる活用推進が急務です。そこで「高岡市空き家・空き地情報バンク」に「空き店舗」も加え、バンク登録物件を活用される場合にインセンティブを付与する支援制度を検討し、より一層、空き家・空き店舗の利活用を推進します。昨年度、中心市街地での年間開業数が過去最大になるなど、シャッター商店街に風が吹きつつあります。今後は条件を設けた上で、開業から数年間の家賃助成などの新たな補助制度を検討するなど、この風をより大きく強くしていきます。
-
時代が変わったからこそ生まれる「令和のまちなか賑わい」創出
時代が変わったからこそ生まれる「令和のまちなか賑わい」創出「俺たちが若いころは街中で肩と肩がぶつかるぐらいだった」過去の街中の賑わいを象徴するお話をよく聞かせてもらいます。昭和の高岡を現す歴史の1ページだと思っています。では令和の時代に同じ町へと戻れるのか、それとも今の時代だからこその賑わいを生んでいくのか。私は人口減少、少子化、消費行動の変容などを分析した上で、昭和の中心市街地に戻るのではなく、今の時代にあった賑わいを求め、まちづくりを進めていくことが肝要だと思います。過去への回帰ではなく、現実を受け入れ、今後目指すべき姿を明確にして突き進みます。まずは、街中でのカーボンニュートラルの実現による付加価値の高い中心市街地を目指し、街なかショールームや体験施設など、まちの新たな賑わいを創出します。
-
カーボンニュートラルや女性活躍など企業が次代を創る挑戦を支える施策の充実
カーボンニュートラルや女性活躍など企業が次代を創る挑戦を支える施策の充実企業を巡ってはSDGsやカーボンニュートラル、女性や障がい者の積極的な雇用など様々な挑戦が求められています。企業にとって、現状維持は大切な事ではありますが、新たな挑戦こそ、持続性を高め、次の時代にも求められる企業への進化に繋がると考えます。これまで社会的課題に果敢に挑戦する企業を支援すべく、補助金の要件を見直してきましたが、今後も進化を目指し挑戦する企業がますます増えるように、支援制度の充実に努めます。
-
「青春インターン」「キワプロ」など学生と企業をつなぐ施策の強化
「青春インターン」「キワプロ」など学生と企業をつなぐ施策の強化企業のトップとお話をする中で、人材確保が難しいとの相談を多く受けます。一方で、各企業に地元高校生をはじめとした地元採用について質問すると高校等に求人を出しても採用に到らないケースが多いとのことでした。企業と高校生をいかにマッチングしていくかが鍵と考え、これまで高校生のインターンシップ「青春(アオハル)インターン」や企業と若者(学生)が一緒に課題解決策を考える「キワプロ」などの事業を展開してきました。高校生が地元の企業を知り、企業が抱えた課題に対して、どのような挑戦をしているのか、また企業側は高校生が何を重要視してこの先の進路を決めようとしているかなど、これまではなかった繋がりが生まれ始めています。今後も企業と学生を進路の決定前につなぎ、互いの考えを理解し合うことができる事業を推進して参ります。
-
テクノドームへのコンベンション誘致や平日利用支援の継続等による利活用策の推進
テクノドームへのコンベンション誘致や平日利用支援の継続等による利活用策の推進テクノドームの別館建設を巡っては紆余曲折ありましたが、建設方針が決まり、令和10年度中の完成を目指す方針です。「県の施設だから…」ではなく、大切な県民の税金で建てられる施設であり、これを建設地である本市が有効活用しない手はありません。県西部の経済発展を目指す拠点として、企業、各種団体が自分の持ち場の中で、この施設を使って何ができるのかを真剣に考え、自ら誘致に動く機運を高めていかなければなりません。行政も共に考え、誘致に向け動くことはもとより、コンベンション実施に対する助成制度を検討するほか、現在、高岡市独自で実施している平日利用への助成制度を継続し、より多くの方が多目的に利用して頂ける施設になるよう県と共に利活用策を推進してきます。
-
公共交通を守る!運転手体験型施策の展開と確保策への支援強化
公共交通を守る!運転手体験型施策の展開と確保策への支援強化公共交通の利活用を進める中、深刻なのは電車、バス、タクシーの運転手不足です。ニーズがあっても運転手がいなければ公共交通で生活はできません。小さいころ、子供たちは「はたらく車」に憧れ、将来の夢を描く子も沢山います。成長するにつれ、その憧れが色褪せ、最終的には選ばれない職業になっています。運転手を憧れの職業にしていくためには公共交通を守る事の意義ややりがい、給与面を含め魅力的な職業でなければなりません。公共交通は公共インフラとの考えを市民と共有し、「運転手になりたい」と思ってもらえる人材の確保に向け、運転手の勤務内容のイメージをより具体的に持ってもらえる体験型の施策に取り組むなど、交通事業者とともに人材確保に向けて支援を強化します。
-
人材不足を克服し持続可能な体制整備へ 担い手確保策への支援強化
人材不足を克服し持続可能な体制整備へ 担い手確保策への支援強化人口減少社会において、担い手不足はどの業界も懸案事項であり、強い経済の構築のためには避けては通れない課題です。高岡市では保育士不足の解消を目指し、本市の民間保育園へ就職された方に最大60万円支給する「保育士等就労助成事業」を実施していて、事業開始2年目にして、年間50人を超える人財確保に繋がりました。今後はこの制度を検証しつつ、人材不足が著しい他の業界への転用についても検討し、人口が減少する中においても持続可能な体制整備に向け、支援して参ります。
-
「伝統産業のツギノテ」伝統産業コーディネーターの育成や受給マッチング会の実施
「伝統産業のツギノテ」伝統産業コーディネーターの育成や受給マッチング会の実施高岡市には銅器、漆器といった大切な伝統産業があります。一方で、生活様式の変化から出荷額は年々減少の一途を辿り、大切な技術を継承する担い手の不足にも陥っています。アメリカを訪問した際、リュックの中に高岡の伝統産業品を詰めていき、セレクトショップやバイヤーに飛び込み営業をかけ、直接商品に触れてもらい、アメリカでの販売の可能性をヒアリングしてきました。製品の質や技術の高さに対する高い評価をいただく反面、価格と用途に対しては率直な意見もいただきました。復活の可能性は十分にあります。様々な課題解決を目指し、事業者間を結ぶ伝統産業コーディネーターを育成し、これまでなかった「間」を繋ぐことに挑戦します。地域おこし協力隊の制度を活用し、挑戦しやすい環境を創出し、伝統産業の裾野を拡げていきます。また、伝統産業の出荷額増加を目指し、「デザイナーと職人」「需要と供給」など様々なマッチングを行う事業をスタートするなど、伝統産業が培った世界に誇る技術の応用を進め、出荷額増を目指し、次の手を打っていきます。
-
高岡商工会議所「ユニティカル」と共に女性創業者への伴走支援の実施
高岡商工会議所「ユニティカル」と共に女性創業者への伴走支援の実施人口の半分以上が女性である高岡において、女性の活躍は本市の発展に直結しています。これまでに「女性人材バンク」の設置やTASUにおいて女性が起業しやすい環境整備に努めるとともに、市の女性幹部と商工会議所女性部との意見交換の場を設け、女性経営者や起業家への効果的な支援について検討して参りました。商工会議所内に女性職員が発案した女性創業者支援チーム「ユニティカル」が編成され、より女性創業者が生み出されやすい環境が整いました。今後はユニティカルと連携し、一人でも多くの女性経営者や起業家が生まれる環境を整備して参ります。
-
スタートアップ施設「TASU」を実証実験の場に進化
スタートアップ施設
「TASU」を実証実験の場に進化令和5年3月にオープンしたスタートアップ支援施設「TASU」には私の様々な思いを詰めて設置しました。行政のハコモノに対する市民の印象は「ハコを作る事が優先で、利活用策は後回し」でした。私は「今の高岡市の課題解決に必要な機能は何か。どの様な使い方ができるのか。それを果す上でどの様な施設が必要か。」この順番に考えます。まさにそれを具現化したのがTASUです。起業創業支援に加え、中心市街地の賑わいや若者支援、学生の勉強スペース確保など複数の社会的課題を解決する施設として、役割を果たしてくれています。今後はさらに多くの課題を解決ができるように様々な実証実験の場としての役割も担い、企業や団体、地域の課題をビジネスの力で解決する事ができるまちを目指していきます。
-
御旅屋人マーケットやたかおか朝市等、市民が行きたくなる商店街づくり
御旅屋人マーケットやたかおか朝市等、市民が行きたくなる商店街づくり市内各地域から中心市街地に行きたくなる用事を作らなければ街中の賑わいは生まれないとの考えのもと、まずは御旅屋通りを人が交流する場所へ変貌させることを目指しスタートしたのが「御旅屋人マーケット」です。道路の半分を人工芝で覆い、普段は味わえない特別な空間を演出します。当初、冬季は実施しない方向で調整していましたが、参加される事業者の方々から「年間を通してやりましょう!」との前向きなご提案をいただき、年間を通して実施する事になりました。前向きな市民からの提案は大歓迎です。今後も大人気のたかおか朝市や中心市街地で開かれるイベントの集客力を商店街の集客に繋げる施策を展開し、市民が行きたくなる商店街を目指して進んで参ります。
市民に役立つ所があるまち(10策)
-
10年、20年を見据えた柔軟で筋肉質な財政構造の確立
10年、20年を見据えた柔軟で筋肉質な財政構造の確立コロナ禍を経て、線状降水帯による大雨災害や能登半島地震からの復旧復興など、直面する課題が山積する中にあっても、市民が希望を持って豊かに暮らせるまちを構築しなければなりません。そのためには行政は市民の皆様からお預かりした税をいかに効率的に市民サービスとして還元していくかが問われています。これまで以上に知恵を出し、工夫を凝らして、市全体を見つめながら、10年20年先の財源を見極め、政策的投資を実施していく必要があります。必要財源を借金(市債)だけに頼るのではなく、基金の効果的活用や外部からの寄附の募集、さらには民間投資の促進など、地域や企業などのステークホルダーと一層の連携を強化することで、柔軟で筋肉質な財政構造を作りあげていきます。
-
将来世代への負担軽減のための市債残高の着実な減少
将来世代への負担軽減のための市債残高の着実な減少市長に就任以降、徹底した無駄の排除や業務の効率化を行い、市債残高は1000億円から800億円台半ばまで減少しました。市民サービスを維持しつつ、将来への負担を軽減するという二兎を追う形となりましたが、市民や企業の挑戦が活発に行われ、税収が増えた事も大きな要因です。次世代がここ高岡でやりたい事に投資をすることができるようにするためにも今の時代で一定程度まで市債を減らしておくことは今を生きる私たちの責任ではないでしょうか。「私たちの税金を借金返済に使うな!」「今の時代に投資しろ」などの御意見もあると思いますが、「子どもに借金を残したくない」という思いは家庭では当たり前だと思いますし、行政も身の丈に合わない借金を後世に引きつぐわけにはいきません。今後も着実に市債を減らしていくとの想いを持って、財政運営に当たります。
-
民間経験のある即戦力職員の採用強化
民間経験のある即戦力職員の
採用強化社会人採用枠を拡大し、民間経験を持つ職員の採用を積極的に行ってきました。警察官や民間航空会社勤務、ソフトウエアの開発者や民間の窓口業務経験者などこれまで行政にはいなかった人財が増え、その影響が市役所で芽吹き始めています。行政には足りていない経験を持つ職員は新しい風を吹かします。市役所内の知識や経験に民間感覚が確実に根付き始めており、この流れを更に強化し、今後も加速していきます。
-
地域活動に参加しやすい環境整備等による地域を愛する職員の育成
地域活動に参加しやすい環境整備等による地域を愛する職員の育成一昔前は希望者の多かった公務員も現在は志願者が減少傾向にあります。入庁時は「高岡市のために」と高い志を持った職員も日々の業務に追われ、当初の志が薄まる人もいます。人が成長しない組織に持続性はなく、人が育つ職場作りにも取り組んでいます。しかし、市役所内だけでの成長では市民目線が養われません。職員は市民であり、地域で暮らす住民です。普段から自治会やPTA等、地域住民として地域活動に参画し、市職員の立場ではなく、地域住民として地域と関わり、住民と触れ合う事で、新たな気づきや学びも多いと思います。職員が地域活動に参加しやすい環境を整え、「高岡市のために」との高い志を持ち続け、地域を愛する職員を育成して参ります。
-
「手の中に市役所を」どこでも市役所シリーズによる市民サービスDX推進
「手の中に市役所を」どこでも市役所シリーズによる市民サービスDX推進「市民の大切な時間を市役所に費やして欲しくない」といつも考えています。デジタルの力を活用し、市役所を訪れなくても行政サービスを受けられる環境を整備する「どこでも市役所シリーズ」を打ち出し、現在までに18件のサービスを展開しています。今後もスマホやパソコンで完結するサービスを増やし、市民の利便性向上を図る事はもちろんですが、デジタルが苦手な高齢者等への配慮も考えていかなければなりません。デジタルが苦手な方を意識し、災害時に固定電話に避難情報をお届けするアナログなサービスを開始しました。今後は市役所に行かなくても地域でサービスを受けられるようにしたいと考えており、近くの公民館や地域交流センターでも市民サービスが受けられる環境整備など、デジタルの力も活用しつつ、新しい時代の市民サービスの提供方法を模索していきます。
-
書かない窓口をさらに進化!ワンストップ窓口の実現
書かない窓口をさらに進化!
ワンストップ窓口の実現高岡市役所では今年1月から「書かない窓口」をスタートさせました。市長直結ホットラインでは「待ち時間が長い」「どこに行けばいいのか分からない」といったご意見を多くいただきました。まずはお越しいただき、ご用件を職員が直接お聞きしながら、必要な手続きを進めていく「書かない窓口」を始める事にしました。今後は「迷わせない窓口」「待たない窓口」を推進し、将来的な目標である「ワンストップ窓口」を目指して、これからも市民目線の市役所窓口改革を進めます。
-
より特色ある施設を目指して 博物館・美術館の一体整備の方針策定
より特色ある施設を目指して 博物館・美術館の一体整備の方針策定郷土の歴史的資料を保管する博物館と金工や漆芸など高岡が育んだ多くの美術品を持つ美術館には高岡市ならではの親和性があり、これらを一体的に配置する事で、「郷土の技を鑑賞し、歴史を学んで郷土愛を培う事ができる」といった本市ならではの特色ある施設に生まれ変われる可能性があります。博物館の老朽化が著しい中、早期に方針を固め、進めなければならない課題でもあります。有識者の方々のご意見も伺いながら、博物館・美術館の一体整備に向けた方針を策定して参ります。
-
半世紀に一度のプロジェクト 時代に求められる市役所庁舎整備
半世紀に一度のプロジェクト 時代に求められる市役所庁舎整備現在の市役所庁舎は築44年を迎え、老朽化は着実に進んでいます。庁舎の一部に耐震強度の不足があることから、有事の際には使用できなくなる事態も想定されます。能登半島地震発災の際には市役所裏手の車庫棟内に対策本部を設け、私を始め、多くの職員は2つの施設を何度も何度も行き来し、対応に当たりました。また、発災直後、「市役所は安全」との誤った認識のもと、多くの市民が一階ロビーに集まって来られ、私自らが説明に向かい、隣接する中学校の避難所へ誘導しました。これまで庁舎については老朽化という観点から検討されていましたが、震災後は防災の視点を加え、可及的速やかに市役所庁舎の今後の在り方を示さなければいけないと考えています。そこで今年2月には新庁舎建設に向けたロードマップをお示しし、令和16年度中の竣工を目指し、今後候補地や建設手法などを市民からのご意見もお聞きし進めていきます。
-
学校跡地の公的活用による高岡市の課題解決策の提示
学校跡地の公的活用による
高岡市の課題解決策の提示五位小学校、高岡西部小学校、高陵小学校が再編統合し、スタートを切っていますが、これまでは子供の学び場の整備・充実を優先し、廃校となった小学校跡地の活用については統合小学校が誕生した後に検討することとなっていました。地域住民にとっては学校跡地の利活用は大きな関心事であり、また様々な憶測が飛び交う案件になっていました。跡地の活用には地域住民の力が必要です。今後の学校再編にあたっては統合小学校の準備と同時に跡地利用についても協議を始めることとしました。まずは伏木地区の再編統合について、行政としての跡地についての考え方をお示ししつつ、地域の理解を得た上で進めていきたいと考えています。先に統合した地区の学校跡地についても民間事業者等へのサウンディング調査などを進めており、複数の学校跡地が動き始めています。投資意欲のある民間の意向も確認しつつ、それぞれの学校跡地について考え方を示していきます。
-
若手職員による高岡市役所営業部の未来投資型事業の展開
若手職員による高岡市役所営業部の未来投資型事業の展開高岡市役所には全国でも珍しい「営業部」があります。高岡市を売り込み、稼ぎを増やすこと、人口減少など高岡市が抱える課題を解決するためのアイディアを入庁10年程度の若手職員が普段の仕事とは別に取り組んでいます。彼らは令和の時代の公務員にならなければなりません。与えられた仕事をやり遂げることはもちろんですが、入庁時に抱いていた「市民を支えたい」「高岡市を発展させたい」といった志を行動で示し、多くの市民から頼られ、時には力をお借しいただける公務員を目指すべきと考え、営業部を立ち上げました。これまでに「たかおかコスプレフェス」や「こどもまんなかフォトコンテストたかおか」などを打ち出し、実際に事業を行っています。地域に飛び出す公務員を具現化し、そこで出会った市民の声やアイディアを施策に変えていく。自分の担当という仕事の枠組みに囚われない、自由な発想とそれを具現化する力を養う営業部から、未来への投資型事業を展開していきます。
Key Policies